特集
サイエンスを“文化”に
サイエンスコミュニケーションの役割は、研究者のようなサイエンスの専門家と一般市民の方のような非専門家との間に、科学の対話の場を生み出すこと。いま、サイエンスコミュニケーションの実践者はどのような考えで市民との対話をしているのでしょうか? 日本科学未来館で勤務後、フリーの科学コミュニケーターとなった本田隆行さん、京都大学iCeMSコミュニケーションデザインユニット長の遠山真理さん、そして京都大学 CiRA国際広報室特定研究員の和田濵裕之さんが語り合いました。

サイエンスに関わることのできる状態をつくる
— みなさん異なる立ち位置から
サイエンスコミュニケーションに
携わっていますが、
それぞれの取り組みを教えてください。
サイエンスコミュニケーションに
携わっていますが、
それぞれの取り組みを教えてください。
遠山 私が所属しているiCeMS(※1)は、京都大学が得意とする材料科学と細胞生物学の分野を超え、生命と物質の境界である研究領域を掘り下げることで、物質−細胞統合科学という新しい研究領域の開拓を目指しています。所内では細胞生物学や材料科学をはじめ、イメージング、情報科学、工学など異分野の研究者たちが、共通言語を模索しながら研究をしています。こうした特徴から、異分野の研究者同士の交流を促すようなサイエンスコミュニケーションに焦点を当てています。
和田濵 私が担当するCiRAの仕事は、 一般の方や患者さんを対象としています。たとえば、このニュースレターなど刊行物の制作や、研究棟内を見学いただく「CiRAツアー」、イベントの開催などです。また、CiRAの研究成果を広く知っていただくために、プレスリリースを作成して配信するほか、マスメディアの方とコミュニケーションを取り、正確な記事を書いていただけるように、支援や工夫をしています。
本田 僕は二人とは少し立ち位置が異なっており、職業としてフリーの立場で科学コミュニケーターをしています。ミッションは「科学技術と“あなた”をつなぐ」こと。活動範囲や手法は限定しておらず、科学・技術の専門家と非専門家の人をつなぐための場を設計することもあれば、企業や組織・団体をつなぐ接点をつくり出すこともあります。
— 「サイエンスコミュニケーションが
成立している」というのは
どういった状態なのでしょう?
成立している」というのは
どういった状態なのでしょう?
遠山 ひとつの明確な答えがあるものではないと思いますが、研究者の頭の中にあるイメージを紙媒体や映像などで表現し、一般の方が何らかの「コメントができる状態」がつくれたとき、私はコミュニケーションができる状態にあると感じますね。
本田 サイエンスコミュニケーションって「科学をわかりやすく伝えること」だと思われているところがあります。でも、僕は意識的に「伝える」という言葉をあまり使わないようにしています。「伝える」が軸になると、伝える側の満足で終わってしまってコミュニケーションを取った気になるだけの場合があるように感じるからです。サイエンスコミュニケーションにおいて重要視しているのは、「やりとりの最中やその後の反応が見られる状況をつくる」ことです。反応が見えると、伝わっているかを推し量ることができるからです。たとえば以前、iCeMSでサイエンスとアートを組み合わせた企画展示『imagination 2.0』(※2)を開催しました。iCeMSの取り組みを知ってもらうために、研究内容をアート作品にして可視化し、作品の前で市民と対話してみようという展示です。
遠山 バス停に面した、iCeMSの正面玄関の廊下で展示を行うというコンセプトはおもしろかったですよね。展示した研究内容を市民のみなさんにとても新鮮に受け取っていただけた。それと同時に、積極的にコミュニケーションを取らないと、市民との距離は離れてしまうんだなとも感じました。
和田濵 イベントや展示で出会う意外性からは、いい気づきをもらえますよね。CiRAでもショッピングモールや地方の科学館などに出張してイベントを開催し、普段出会えない方々とお話しでき、さまざまな気づきをいただきました。私の場合、市民との信頼を築くことを大切にしています。私は研究内容そのものについては、100パーセント伝わらなくてもいいと考えています。それよりも、私たちの目指す方向性を理解いただける、あるいは疑問が生じても解消できるような信頼関係を市民との間につくることを、コミュニケーションのひとつのゴールにしています。
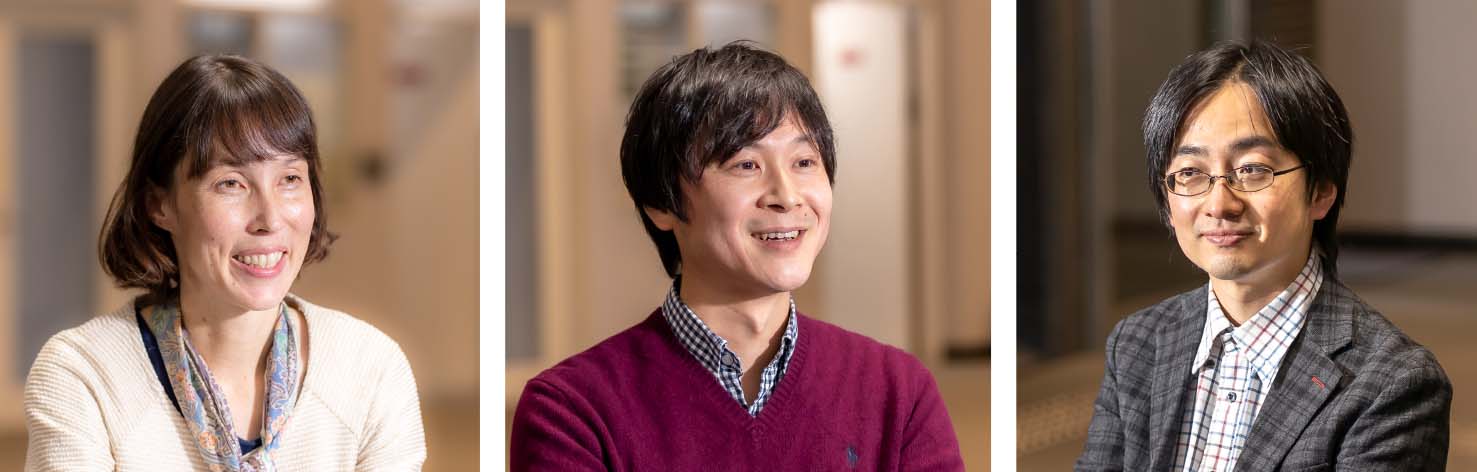
(左から)遠山 真理さん、本田 隆行さん、和田濱 裕之さん
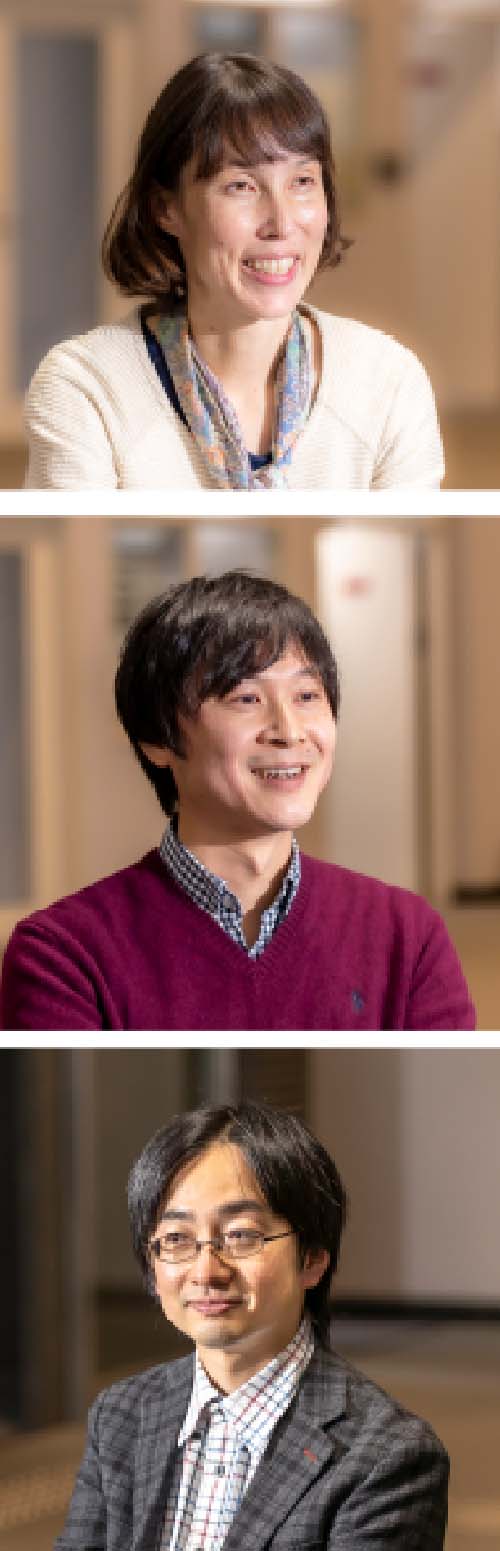
(上から)遠山 真理さん、本田 隆行さん、和田濱 裕之さん
市民との「境界」をいかに溶かすのか
— 「市民との対話」は
サイエンスコミュニケーションでよく用いられる
表現ですが、そもそも「市民」にどのような人を
想定していますか?
サイエンスコミュニケーションでよく用いられる
表現ですが、そもそも「市民」にどのような人を
想定していますか?
本田 僕は自分が市民側の最前列にいるイメージを強めに持って仕事をしています。「アウトリーチ(※3)」や「リテラシー(※4)」といった言葉は、「市民との対話」と同様に、サイエンスコミュニケーションにおいて重視されていることですが、どれもサイエンス側に立つ人の言葉であり、考え方ですよね。コミュニケーションを図りたい市民の多くは、そもそもサイエンスの側に到達するまでにまだ距離がある存在です。だから僕はできるだけ立ち位置を市民の側に寄せて、サイエンス側の人と向き合います。もし少し疑問を抱いたら、すぐに「どういうことですか?」と聞いちゃう。そうして、市民の側とサイエンスの側の境界を溶かして曖昧にしていくことで対話を生み出すイメージですね。
和田濵 本田さんにとって、市民とコミュニケーションを取る場合において、サイエンスは、政治や経済など、他の社会的テーマと比べて特殊なものですか?
本田 違いがあるとしたら、サイエンスは「なんだか難しい勉強」という思いを強く持つ市民が圧倒的に多いという点ではないでしょうか。教養がないと立ち入れない領域だと思われていて、中身がブラックボックス化している。この特殊性を打破する上で大切なことは、関わり方のバリエーションを増やすことですね。スポーツでも、選手の名前を知っていたり、ルールを知っていると、観戦したり自分がプレイしたりして関わることができるようになる。市民が関わる方法を模索できる状態をつくることが、サイエンスというテーマでは一工夫必要ですね。
遠山 実際にはサイエンスに携わっている人も、研究所を出れば一般社会の住人ですからね。サイエンスの恩恵を受けたり、おもしろさに気づいたりする一般社会に自分自身も生きているわけですから、本当は共通言語があるはずなんです。
※ 1 iCeMS(アイセムス) 京都大学アイセムス 物質―細胞統合システム拠点 材料科学と細胞生物学を合成、工学、シミュレーション、イメージングにおける最先端科学と掛け合わせ、「物質― 細胞統合科学」という新研究領域を開拓することを目指している。
※ 2 imagination 2.0 2016年6 月24 日から7 月7 日まで、iCeMS 本館1F 正面玄関の廊下で開催された、サイエンスとアートをかけ合わせた企画展示。iCeMS 科学コミュニケーショングループの馬場美恵子さんが、iCeMSの研究者から提供をうけた画像などの素材をモチーフに制作したアート作品14 点を展示。市民との対話の場を生み出し、会期中には700名以上の市民が訪れた。
※ 3 アウトリーチ 研究者が市民などへ研究成果を紹介すること。
※ 4 リテラシー 原義としては読み書き能力を指すが、現代では、特定分野の知識体系を理解し、活用する能力のことも指す。
※ 2 imagination 2.0 2016年6 月24 日から7 月7 日まで、iCeMS 本館1F 正面玄関の廊下で開催された、サイエンスとアートをかけ合わせた企画展示。iCeMS 科学コミュニケーショングループの馬場美恵子さんが、iCeMSの研究者から提供をうけた画像などの素材をモチーフに制作したアート作品14 点を展示。市民との対話の場を生み出し、会期中には700名以上の市民が訪れた。
※ 3 アウトリーチ 研究者が市民などへ研究成果を紹介すること。
※ 4 リテラシー 原義としては読み書き能力を指すが、現代では、特定分野の知識体系を理解し、活用する能力のことも指す。
サイエンスを文化へ翻訳する
— コロナ禍によって
サイエンスの社会的認識が高まっているとされています。
今後サイエンスコミュニケーションには
どのようなことが求められていくのでしょうか?
サイエンスの社会的認識が高まっているとされています。
今後サイエンスコミュニケーションには
どのようなことが求められていくのでしょうか?
本田 現在のサイエンスに対する社会的認識の向上がコロナ禍が生み出した一過性のブームだとしたら、僕たちの仕事は、この状況をもとに戻さないようにするということかもしれません。もとに戻らないということは、すなわち文化になるということです。たとえば、将棋をたしなまないひとも、棋士の藤井聡太さんのニュースには注目します。これは将棋が文化になっているからです。サイエンスを文化として定着させ、その本質となる部分が社会で議論される状態にしておくことは、サイエンスコミュニケーションのひとつの目標なのだと思います。
遠山 サイエンスを文化に、というのは同感ですね。私は「つくる」ということに、より多く携わりたいと思います。サイエンスコミュニケーションは、「伝える」ことにフォーカスがあたりがちですが、実際にはサイエンスを文化に翻訳するために「つくる」という側面が本質なのだと思います。
和田濵 iPS細胞に関するサイエンスコミュニケーションという視点でいえば、2012年の山中所長のノーベル生理学・医学賞受賞などで過度に期待が先行していた社会認識が、落ち着いてきている印象があります。iPS細胞は特殊な事例でもあり、知名度と期待値が高い半面、中身が市民へ十分に伝わっていなかったと思います。最近では医療応用に近い段階に至った研究もあり、ますますコミュニケーションが求められます。私たちがこれから進めていかなければいけないことは、市民からの声に対して耳を傾け、対話を通してひとつずつ相互に理解を深めていく実践を重ねることです。少しずつではあるけれど、確実な信頼を築いていくことが、もっとも大切なことなのではないかと考えています。
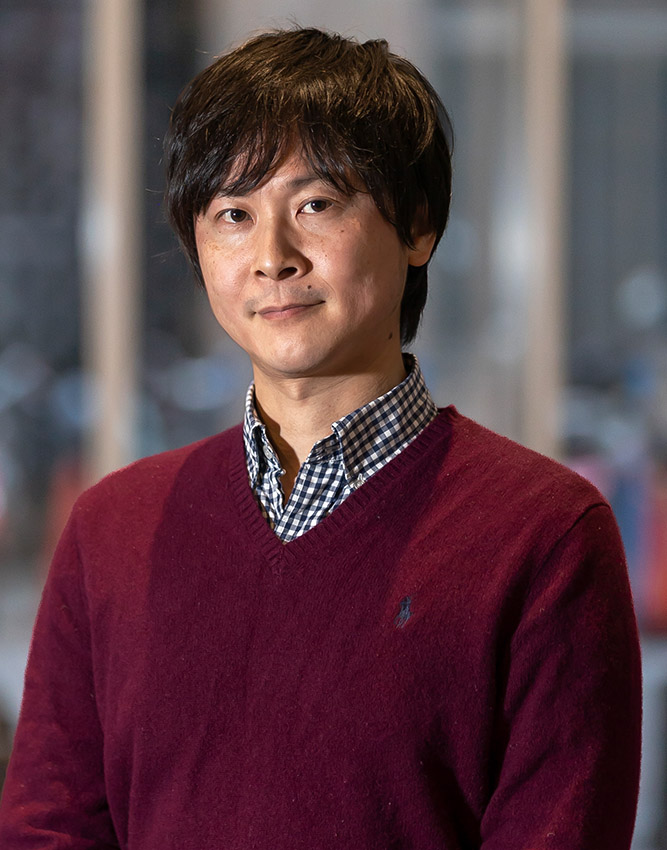
ほんだ たかゆき
本田 隆行
本田 隆行
科学コミュニケーター
神戸大学大学院にて地球惑星科学を専攻(理学修士)。地方公務員事務職、日本科学未来館勤務を経て、2015 年に国内でも稀有なプロの科学コミュニケーターとして独立。「科学技術と“ あなた” をつなぐ」をミッションとして、科学に関する展示企画、実演の実施・監修、大学講師やファシリテーター、行政委員、執筆業、各メディアでの科学解説など、なんでもこなす。著書・監修に『宇宙・天文で働く』(ぺりかん社)、『もしも恐竜とくらしたら』(WAVE出版)など多数。www.sc-honda.com
神戸大学大学院にて地球惑星科学を専攻(理学修士)。地方公務員事務職、日本科学未来館勤務を経て、2015 年に国内でも稀有なプロの科学コミュニケーターとして独立。「科学技術と“ あなた” をつなぐ」をミッションとして、科学に関する展示企画、実演の実施・監修、大学講師やファシリテーター、行政委員、執筆業、各メディアでの科学解説など、なんでもこなす。著書・監修に『宇宙・天文で働く』(ぺりかん社)、『もしも恐竜とくらしたら』(WAVE出版)など多数。www.sc-honda.com

とおやま まり
遠山 真理 特定准教授
遠山 真理 特定准教授
iCeMS コミュニケーションデザインユニット長
2003 年東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻博士課程中退。2011 年までJT 生命誌研究館にてサイエンスコミュニケーターとして活動後、京都大学iPS 細胞研究所にて国際広報室特定研究員(2011 年から2016 年)に。総合地球環境学研究所広報室特任准教授(2016 年から2018 年)を経て現職。
2003 年東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻博士課程中退。2011 年までJT 生命誌研究館にてサイエンスコミュニケーターとして活動後、京都大学iPS 細胞研究所にて国際広報室特定研究員(2011 年から2016 年)に。総合地球環境学研究所広報室特任准教授(2016 年から2018 年)を経て現職。

わだはま ひろゆき
和田濵 裕之
和田濵 裕之
CiRA 国際広報室 特定研究員
2010 年京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻博士課程修了。博士課程ではダイズタンパク質について研究し、遺伝子組換ダイズの一般認識と研究者の認識に大きな乖離があることに気づき、科学コミュニケーションの分野に進む。2011 年理化学研究所発生再生科学総合研究センター(当時)にて科学コミュニケーションの実務に携わり、2012年より現職。
2010 年京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻博士課程修了。博士課程ではダイズタンパク質について研究し、遺伝子組換ダイズの一般認識と研究者の認識に大きな乖離があることに気づき、科学コミュニケーションの分野に進む。2011 年理化学研究所発生再生科学総合研究センター(当時)にて科学コミュニケーションの実務に携わり、2012年より現職。