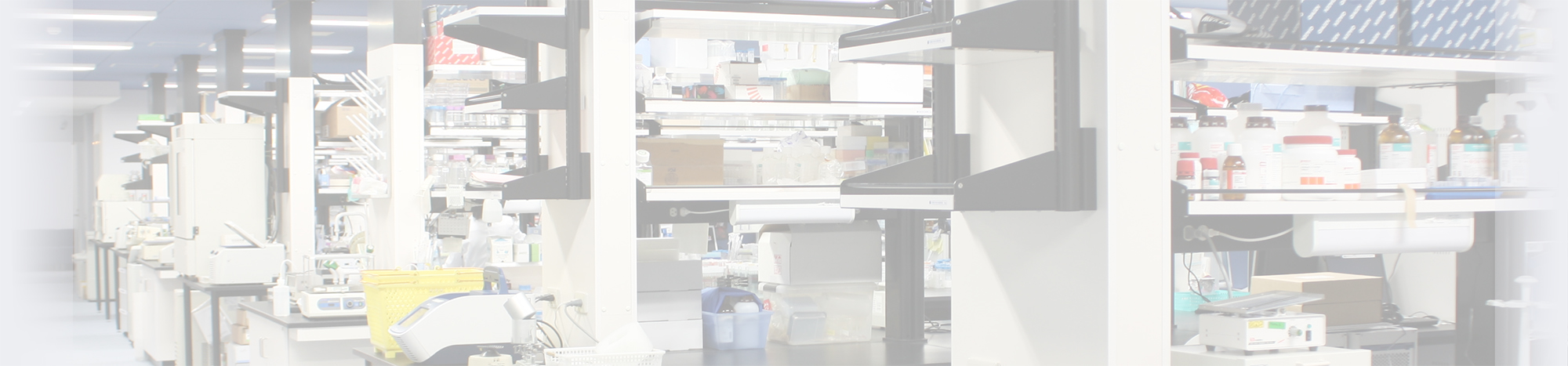
研究活動
Research Activities
研究活動
Research Activities
研究成果
Publications
2011年6月9日
転写因子Glis1により安全なiPS細胞の高効率作製に成功 Nature 6月9日号に掲載
前川桃子助教(京都大学ウイルス研究所/同iPS細胞研究所/JST山中iPS細胞特別プロジェクト)と山中伸弥教授(京都大学物質-細胞統合システム拠点/同iPS細胞研究所/JST山中iPS細胞特別プロジェクト)の研究グループは、五島直樹主任研究員(産業技術総合研究所バイオメディシナル情報研究センター/NEDO iPS細胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発)の研究グループとの共同研究で、卵細胞で強く発現する転写因子注1)Glis1を用いると、従来の方法に比較して非常に効率よくiPS細胞(人工多能性幹細胞)注2)を誘導できることを発見しました。

左から前川助教、山中教授、五島主任研究員
従来は、レトロウイルスベクター注3)で4つの転写因子(Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc)を線維芽細胞注4)に導入してiPS細胞を作製していましたが、原がん遺伝子c-Mycによる腫瘍発生が懸念されていました。また、c-Mycなしでの誘導では、作製効率が低いこともあり、安全なiPS細胞を効率よく誘導する方法の開発が望まれていました。本研究では、iPS細胞誘導に関与する新規因子の探索を行い複数の因子を同定しましたが、そのうちのGlis1を3因子(Oct3/4, Sox2, Klf4)と一緒に、マウスまたはヒトの線維芽細胞にレトロウイルスベクターを用いて導入したところ、いずれにおいてもiPS細胞の樹立効率が顕著に改善されました。さらに、Glis1は初期化が不完全な細胞の増殖を抑制し、完全に初期化した細胞のみ増殖することを明らかにしました。また、Glis1が初期化を促進する機構についても詳細な解析を行いました。今回発見された転写因子Glis1とそこから得られた知見は、将来の臨床応用に役立つことが期待されます。
本共同研究は、科学技術振興機構(JST)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の機関が省庁の垣根を越えた連携のもとでの支援を受け実施されました。この研究成果は、英国科学誌「Nature」6月9日号に掲載されました。
- 論文名
Direct reprogramming of somatic cells is promoted by maternal transcription factor Glis1 - ジャーナル名
Nature - 著者
Momoko Maekawa, Kei Yamaguchi, Tomonori Nakamura, Ran Shibukawa, Ikumi Kodanaka, Tomoko Ichisaka, Yoshifumi Kawamura, Hiromi Mochizuki, Naoki Goshima, and Shinya Yamanaka
注1)転写因子
たんぱく質合成は、DNA上の遺伝子を鋳型にしてメッセンジャーRNA(mRNA)が転写され、このmRNAが核外のリボソーム上で翻訳される過程で成り立っている。転写因子は、転写開始に関わる因子で、DNAに結合して働くものや因子間の相互作用によって機能するものがある。
注2)iPS細胞
人工多能性幹細胞(iPS細胞:induced pluripotent stem cell)のこと。皮膚などの体細胞に特定因子を導入することにより作製される。胚性幹細胞(ES細胞)のように無限に増え続ける能力と体のあらゆる組織細胞に分化する能力を有する多能性幹細胞である。
注3)レトロウイルスベクター
ベクターとは、細胞外から内部へ遺伝子を導入する際の「運び屋」を指す。ウイルス由来のベクターは、遺伝子導入効率の高さから盛んに開発されてきた。目的遺伝子をウイルスに組み込み、細胞に感染させることにより遺伝子を導入する。レトロウイルスベクターは、このウイルスベクターの1種類として確立されたもので、宿主の細胞に感染したあと、宿主のDNAのなかに入り込み、自らのウイルスを増殖させる性質を利用するものである。
注4)線維芽細胞
皮膚などから得られる細胞の一種。






















