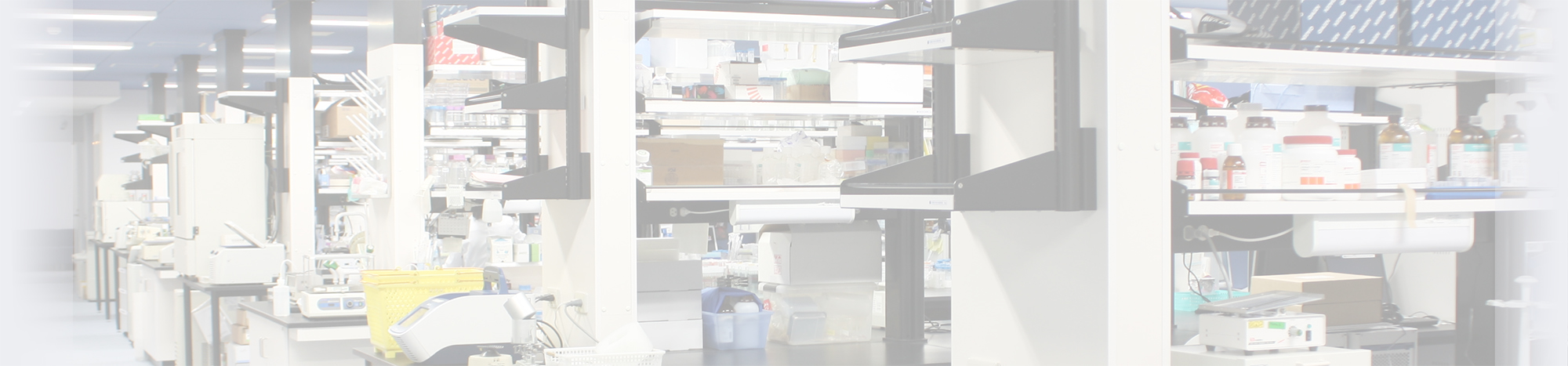
研究活動
Research Activities
研究活動
Research Activities
研究成果
Publications
2016年6月24日
iPS細胞により家族性パーキンソン病であるPerry症候群の病態の一部再現に成功
ポイント
- Perry症候群注1は病態に未解明の部分が多く、確立した病態モデル注2の報告はない。
- Perry症候群患者さん由来のiPS細胞からチロシンハイドロキシラーゼ(TH)陽性細胞注3を作製し、病態の一部を細胞レベルで再現した。
- Perry症候群の発症メカニズムの解明や新薬開発にとって大きな一歩である。
三嶋崇靖助教・大学院生(福岡大学病院、元・福岡大学病院助手、元・京都大学CiRA特別研究学生)と井上治久教授(京都大学CiRA増殖分化機構研究部門)らの研究グループは、家族性パーキンソン病注4の一種であるPerry症候群の病態の一部の再現を、患者さん由来のiPS細胞を用いることにより成功しました。
Perry症候群は孤発性パーキンソン病注4と比較して経過が早いのが特徴です。Perry症候群は、ダイナクチンというタンパク質をつくる遺伝子に変異があり、患者さんの神経細胞、主にドパミン神経細胞(TH陽性細胞)にダイナクチンやTDP-43というタンパク質の凝集体がみられることがわかっています。本研究では、患者さんから作製したiPS細胞を用いて、TH陽性細胞を分化誘導しました。このTH陽性細胞には、Perry症候群病理組織内で見られる神経細胞と類似のダイナクチンの凝集体が観察されました。
以上の結果から、Perry症候群患者さん由来のiPS細胞から分化誘導したTH陽性細胞は、Perry症候群の病態モデルとして有効である可能性が示され、今後の病態解明や新薬開発が加速することが期待されます。
この研究成果は2016年6月15日に「Parkinsonism & Related Disorders」でオンライン公開されました。
Perry症候群は手足のふるえ、バランスの悪さ、動きのにぶさ、筋肉のかたさなどのパーキンソニズム(パーキンソン様症状)、うつ症状、体重減少、呼吸障害をきたす遺伝性の疾患で、発症年齢が40歳代と若く、約5年の経過で死に至る疾患です。これまで、培養細胞を用いた研究で、Perry症候群の遺伝子変異をもつ細胞においてダイナクチンの凝集体がみられることは観察されていました。しかし、これらの研究は、患者さんの遺伝子を過剰に発現させた細胞モデルであり、患者さん由来の細胞でのモデル作製が求められていました。また、これまでにPerry症候群患者さんからiPS細胞を作製した報告はありませんでした。
3. 研究結果
1)F52L変異のPerry症候群の臨床症状の検討
Perry症候群の原因には、ダイナクチン遺伝子の複数の変異が報告されています。本研究では、ダイナクチン遺伝子のF52L変異(指定される52番目のアミノ酸が、フェニルアラニンからロイシンに変わる変異)をもつ1名のPerry症候群患者さんの臨床症状を詳細に検討し、孤発性パーキンソン病に類似したパーキンソニズムがみられることを明らかにしました。また、脳ドパミントランスポーターシンチグラフィ注5の取り込み低下を認め、この患者さんの疾患標的細胞がドパミン神経細胞であることを示しました。
2)Perry症候群患者さん由来のiPS細胞を用いて病態の一部を再現
Perry症候群に罹患していない方1名から作製した対照iPS細胞とF52L遺伝子変異をもつPerry症候群患者さん1名から作製したiPS細胞から、それぞれTH陽性細胞へと分化誘導させたところ、Perry症候群患者さん由来の細胞でのみダイナクチンの凝集体がみられ、患者さんの病態の一部を再現しました。
4. まとめ
本研究では、Perry症候群の患者さん由来のiPS細胞からTH陽性細胞に分化誘導し、Perry症候群の病態の一部を再現することに成功しました。今後は、他の遺伝子変異によるPerry症候群の患者さんでも同様の結果が得られるか検討を行うとともに、患者さん由来の細胞を用いて病態の更なる解明および治療薬探索基盤を進化させる必要があります。
- 論文名
"Cytoplasmic aggregates of dynactin in iPSC-derived tyrosine hydroxylase-positive neurons from a patient with Perry syndrome" - ジャーナル名
Parkinsonism & Related Disorders - 著者
Takayasu Mishima1, 2, Taizo Ishikawa1, 3, Keiko Imamura1, Takayuki Kondo1, Yasushi Koshiba1, 4, Ryosuke Takahashi4, Jun Takahashi1, Akihiro Watanabe5, Naoki Fujii5, Yoshio Tsuboi2, and Haruhisa Inoue1 - 著者の所属機関
- 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)
- 福岡大学医学部神経内科
- 大日本住友製薬
- 京都大学大学院医学研究科神経内科
- 独立行政法人国立病院機構大牟田病院神経内科
本研究は、下記機関より資金的支援を受けて実施されました。
- AMED再生医療実現拠点ネットワークプログラム疾患特異的iPS細胞を活用した難病研究
- 日本学術振興会 科研費 若手研究(B)
- AMED再生医療実用化研究事業
- AMED再生医療実現拠点ネットワークプログラムiPS細胞研究中核拠点
- 公益財団法人 持田記念医学薬学振興財団 財団設立30周年記念助成
- 公益財団法人第一三共生命科学研究振興財団・研究助成
-
注1)Perry症候群
手足のふるえ、バランスの悪さ、動きのにぶさ、筋肉のかたさなどのパーキンソニズム、うつ症状、体重減少、呼吸障害をきたす遺伝性の病気で、呼吸障害で亡くなる方が多い。主にドパミン神経細胞に異常を生じることによる。現在、有効な治療法は確立されておらず、指定難病の一つである。
-
注2)病態モデル
病気に特徴的な症状や性質を再現したもの。研究を行う際には、病態モデルを用いて病気の原因究明や治療薬の開発を行う。これまでも病態を再現した実験動物が、病態モデルとして多くの基礎研究に利用されていた。ヒトの疾患特異的iPS細胞から病態が再現できれば、ヒト細胞を用いた基礎研究が大きく進展することが期待されている。
- 注3)チロシンハイドロキシラーゼ(TH)陽性細胞
チロシンハイドロキシラーゼという酵素もつ神経細胞のこと。THは、カテコールアミン代謝の第一段階を触媒する酵素であり、ドパミン神経細胞で発現している。この神経細胞が変性・死滅することで手足のふるえ、バランスの悪さ、動きのにぶさ、筋肉のかたさなどのパーキンソニズムの症状がみられる。
-
注4)家族性パーキンソン病、孤発性パーキンソン病
パーキンソン病は家族性と孤発性の2種類にわけられる。家族性パーキンソン病は遺伝子異常が要因である一方、孤発性パーキンソン病は遺伝子以外の要因がある推測されている。家族パーキンソン病は孤発性パーキンソン病と比較して発症年齢が若いことが多い。
-
注5)脳ドパミントランスポーターシンチグラフィ
画像検査の一つで、患者さんの脳内のドパミン神経細胞の変性を推測することができる検査のこと。パーキンソン病では、神経細胞終末に存在するドパミントランスポーター(DAT)密度が低下していることが知られており、その密度を測定することでドパミン神経の変性を推測することができる。






















