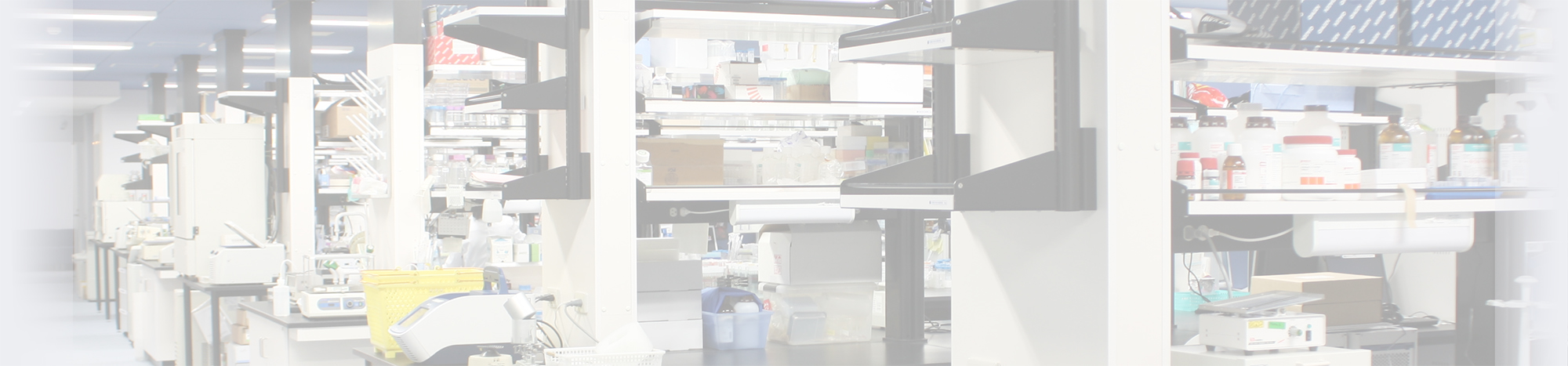
研究活動
Research Activities
研究活動
Research Activities
研究成果
Publications
2025年8月5日
機械学習による視床下部-下垂体オルガノイド分化効率予測モデルの構築
ポイント
- 機械学習を用いて、ヒトiPS細胞から下垂体オルガノイドへ分化する効率を予測するモデルを構築
- 本モデルは、熟練実験者と比べても高い予測精度を示した
- 予測にはオルガノイド表面の性状が重要であり、これらの違いは細胞種の違いを反映している
松本 隆作 特定拠点助教(CiRA未来生命科学開拓部門)、山本 拓也 教授(CiRA未来生命科学開拓部門)らの研究グループは、ヒトiPS細胞から視床下部-下垂体オルガノイド注1)を分化誘導する実験系において、培養初期に取得した位相差画像のみから、1ヶ月後の分化効率を予測可能な機械学習注2)モデルを構築しました。この研究成果は2025年8月4日「Cell Reports Methods」で公開されました。
ヒトiPS細胞からさまざまな標的細胞のオルガノイドを分化誘導する手法が開発され、再生治療、病態研究、創薬などへの応用が進んでいます。しかしながら、下垂体ホルモン産生細胞のように十分な機能を備えた細胞を得るまでには、2~3ヶ月に及ぶ長期間の培養が必要です。さらに、視床下部細胞と下垂体細胞の両方をバランスよく誘導する必要があるため、分化効率にはばらつきが生じやすく、その安定性が課題となってきました。
そこで本研究グループは、培養初期の段階で最終的な分化効率を予測できれば、実験者の労力やコストの大幅な削減につながると考えました。この目的のもと、培養初期に取得した位相差画像のみを用いて分化効率を予測する、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)注3)モデルの構築に取り組みました。
1)視床下部-下垂体オルガノイド予測モデル構築
本分化誘導法では、培養開始から約40日目にLHX3陽性の下垂体前駆細胞の分化が確認できれば、その後、60-90日で下垂体ホルモン産生細胞の分化が概ね達成できることが知られています。そこで本研究では、培養初期に取得した位相差画像からLHX3陽性下垂体前駆細胞の分化効率を予測するモデルの構築を目指しました。
まず、LHX3陽性細胞がmCherry蛍光を発するように設計されたレポーターiPS細胞株を樹立し、分化効率を可視化・定量できる実験系を確立しました。次に、培養開始後3、9、15、21、27日目の位相差画像を取得し、39日目にmCherry蛍光の有無を観察することで、各オルガノイドが分化に成功したか否かを分類しました。各日ごとに約1,300枚の画像データを収集し、既存の画像認識モデルであるVGG16をファインチューニングすることで、予測モデルを構築しました(図1A)。特に、培養9日目および15日目の画像を用いたモデルでは、予測精度約80%、AUC 0.83-0.84と高い性能を示しました。これらの予測精度は熟練した実験者による判断を大きく上回るものでした(図1B-D)。

図1:下垂体オルガノイド形成予測モデルの構築とその予測精度
A. 予測モデル構築の手順
B. VGG16のファインチューニングによる予測モデルの予測精度. acc: モデル構築用データに対する予測精度. val_acc: 精度測定用データに対する予測精度
C. 培養9日目、15日目の画像データに基づくAUC曲線
D. 機械学習モデルと熟練した実験者による予測精度の比較
2)予測根拠の推定
本学習モデルがどのような情報に基づいて分化効率を予測しているのかを明らかにするため、Grad-CAM(Gradient-weighted Class Activation Mapping)注4)を適応したところ、培養日数や分化の成否にかかわらず、本モデルはオルガノイドの表面構造に着目していることが明らかになりました(図2A)。次に、オルガノイド表面の性状の違いがどのような細胞構成の違いを反映しているのかを明らかにするため、免疫染色を行いました。その結果、分化に成功したオルガノイドでは、Grad-CAMで寄与度の高いとされた領域に口腔外胚葉細胞が誘導されていたのに対し、分化が不十分だったオルガノイドでは、神経細胞や非特異的な細胞が認められました(図2B)。これらの結果から、オルガノイド表面の性状の違いは、分化の成否に関連する細胞種の違いを反映しているものと考えられます。

図2. Grad-CAMによるアテンションマップ
A. 培養9日目および15日目における予測モデルのGrad-CAM画像
B. Grad-CAMで寄与度が高いとされた領域に対応する免疫染色像
3. 分化誘導の成否によるオルガノイドの違い
最後に、分化に成功したオルガノイドと、分化が不十分だったオルガノイドの比較解析を行いました。これらのオルガノイドにおける遺伝子発現を比較したところ、分化が不十分だったオルガノイドでは、神経細胞や神経網膜細胞など、視床下部-下垂体系の発生に直接の関与しない細胞の遺伝子発現が上昇していまし(図3A)。また、分化が不十分だったオルガノイドでは、実際にこれらの細胞種がオルガノイド表面に高頻度で存在することが免疫染色により明らかになりました(図3B)。

図3. 分化の成否によるオルガノイドに含まれる細胞種の検討
A. 中枢神経細胞および神経網膜細胞のマーカー遺伝子発現解析
B. 神経幹細胞および神経網膜細胞マーカーに対する免疫染色像
本研究では、培養初期に取得した位相差画像のみを用いて、視床下部-下垂体オルガノイドの分化効率を予測可能な機械学習モデルを構築しました。本モデルは、実験者の負担軽減やコスト削減に寄与するだけでなく、実験のクオリティコントロールや分化効率の高い細胞株の選定といった応用にも有用です。また、本研究成果は、オルガノイドを含む三次元構造体においても、その形態的特徴から内部の細胞種を予測できる可能性があることを示唆しています。この手法は、本研究対象に限らず、他のさまざまなオルガノイドモデルにも広く応用できると期待されます。
- 論文名
Prediction of the hypothalamus-pituitary organoid formation using machine learning - ジャーナル名
Cell Reports Methods - 著者
Ryusaku Matsumoto1,2,3,*,**, Hidetaka Suga4, Yutaka Takahashi2,5, Takashi Aoi3, Takuya Yamamoto1,6,7,**
*筆頭著者 **責任著者 - 著者の所属機関
- 京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)
- 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学
- 神戸大学大学院医学研究科 iPS細胞応用医学
- 名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学
- 奈良県立医科大学 糖尿病・内分泌内科学
- 京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)
- 理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)
本研究は、下記機関より支援を受けて実施されました。
-
日本学術振興会
- 特別研究員奨励費 (21J01689)
- 日中韓フォーサイト事業 (JPJSA3F20230001)
- 日本内分泌学会 研究助成制度
- iPSアカデミアジャパン 研究助成
-
科学技術振興機構 (JST)
- FOREST (JPMJFR206C)
- CREST (JPMJCR2023)
-
日本医療研究開発機構(AMED)
- 革新的先端研究開発支援事業
ヒト新生児期、乳児期アレルギー発症に関与するTfh2反応メカニズムの解明(JP19gm1310002)
幹細胞を利用したヒト初期発生学の創出(JP21gm1310011)- 再生医療実現拠点ネットワークプログラム
再生医療用iPS細胞ストック開発拠点(JP21bm0104001) -
再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム
- 糖尿病根治を目指したMYCLによるリプログラミングを介した膵島再生医療の開発 (JP22bm1223002)
- 次世代医療を目指した再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発拠点(JP23bm1323001)
- 胎盤構成細胞の時空間的動態変化の解明とトロホブラスト幹細胞の機能回復機構の確立(JP24bm1123053)
- 京都大学iPS細胞研究基金 若手研究者育成費
注1)視床下部-下垂体オルガノイド
iPS細胞から誘導され、実際に下垂体ホルモンを分泌する機能的な下垂体ホルモン産生細胞を含む。
注2)機械学習
コンピューターに大量のデータを学習させることで、パターンやルールを抽出させ、予測や分類を行う技術
注3)畳み込みニューラルネットワーク(CNN)
主に画像認識や動体検出に用いられる機械学習モデル。人間の神経構造を模したモデルであり、数十から数百の層から成り、各層で画像の特徴量を抽出する。
注4)Gradient-weighted Class Activation Mapping(Grad-CAM)
CNNの判断根拠の可視化を行う手法。CNNの推論時における寄与度の高い領域を可視化する。






















