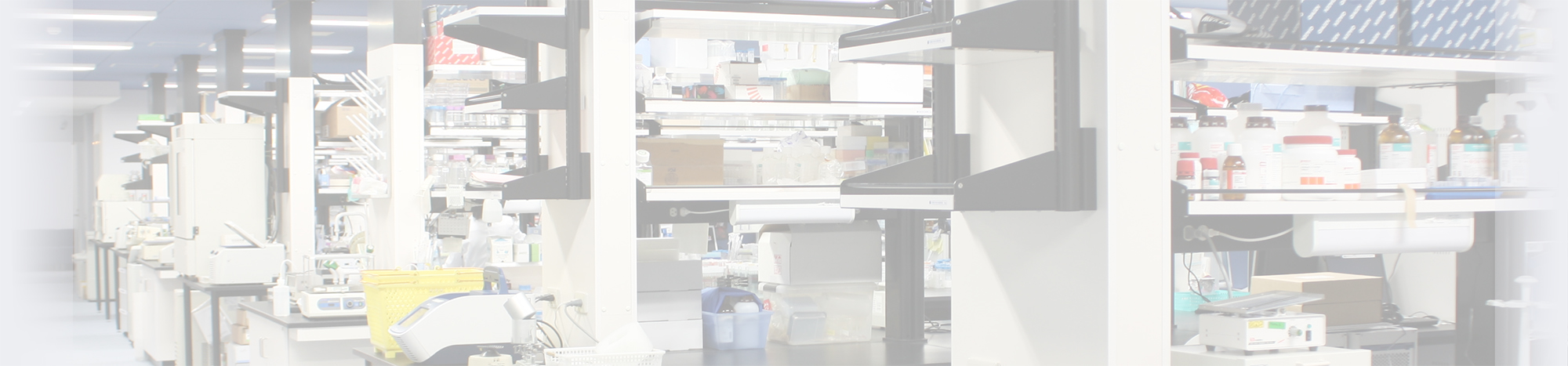
研究活動
Research Activities
研究活動
Research Activities
研究成果
Publications
2016年10月11日
iPS細胞から機能性を保持した血小板を作製する培養方法を構築
ポイント
- 従来の方法では、生体外でiPS細胞から血小板を作る際に血小板機能が損なわれてしまう。
- 臨床応用に向けて、血小板機能を保持する新しい培養添加物KP-457を作製し、より質の高い血小板を作製できるようになった。
平田真治研究員(京都大学CiRA、科研製薬株式会社)、江藤浩之教授(京都大学CiRA)らの研究グループは、iPS細胞から製造した血小板注1)が、止血のために必須な機能を保持できる培養方法を構築しました。これまでにもiPS細胞から血小板をつくることはできていましたが、血小板が傷害血管に接着して機能するために重要なGPIbα注2)というタンパク質が血小板を作製する過程で切断されてしまい、血小板本来の機能が損なわれてしまうという課題がありました。本研究では、GPIbαを切断するADAM17注3)という酵素を選択的に阻害する化合物KP-457を新たに発見し、培養添加物として使用することで、iPS細胞由来の血小板の機能を保持することに成功しました。これにより、臨床応用に向けて、より質の高い血小板を作製することが可能になりました。
この研究成果は2016年10月5日に米国科学誌「Stem Cells Translational Medicine」のオンライン版に掲載されました。
血小板は、生体内で止血を担当する血液細胞で、巨核球という細胞から生み出され、血液の中を循環します。現在、深刻な貧血および出血素因をもたらすような血液疾患の患者さんは、献血による血液製剤を用いた輸血に頼らざるを得ない状況です。しかし、献血ドナーの数は少子高齢化等の影響もあり、減少しています。厚生労働省の統計によると、2027年には、ドナー不足のため、我が国で必要な輸血製剤の20%近くが供給できなくなると発表されています。特に、血小板は、機能を維持するために室温で保存する必要があるため、法令で決められた有効期間が4日と非常に短いことが特徴です。将来の供給不足を補うため、ドナーのみに依存した体制からの脱却を目指して、江藤教授らのグループはこれまでにiPS細胞から生体外で大量の血小板が生産できる方法を提案してきました。細胞の培養は、37℃付近の温度で行われるのが一般的ですが、血小板は37℃ではGPIbαという機能分子がADAM17という酵素に切断され、機能性が低下してしまいます。GPIbαは、傷ついた血管に血小板が接着して止血する際に必要なタンパク質であるため、血小板機能に欠かすことができません。そこで、GPIbαを保持できる培養方法について研究を行いました。
1)新規ADAM17阻害化合物KP-457を用いたiPS細胞由来の血小板のGPIbα保持効果
まず、血小板の保存に適した温度(室温:20−24℃)でiPS細胞由来の血小板が作製できないか検討しましたが、残念ながらうまく血小板を作製できませんでした。そこで、37℃でもGPIbαが切断されない培養方法を構築するため、ADAM17を阻害することを試みました。これまでの私たちの先行研究などで、ADAM17を阻害することでGPIbαの切断を止めることができることはわかっていました(Nishikii et al., J Exp Med., 2008)。一方で、iPS細胞由来の血小板は、将来的に患者さんに輸血することを想定していますので、輸血パック内に持ち越される可能性のある培養添加物は、有効性に加えて安全性を確認する必要があります。そこで、ADAM17以外の酵素をほとんど阻害せず、動物実験で安全性を確認したKP-457という化合物を新規に作製しました。KP-457をiPS細胞由来の血小板を作製する際に添加することで(Fig.1)、37℃でもGPIbαを保持した血小板を作製することが可能になりました(Fig.2)。

Fig.1 iPS細胞からの血小板分化誘導法

Fig.2 ヒトiPS細胞由来の血小板におけるKP-457のGPIbα保持効果
KP-457を添加せずに作製したiPS細胞由来の血小板(左)とKP-457を添加して作製した血小板(右)のGPIbα発現。図中の数字は、GPIbαを発現したiPS細胞由来の血小板の割合を示す。
2)KP-457を添加して作製したiPS細胞由来の血小板の機能解析
次に、従来の方法と比べて、KP-457を添加して作製したiPS細胞由来の血小板の機能性がどの程度向上したか検討しました。リストセチン注4)という物質で刺激して、GPIbαとフォンウイルブランド因子(vWF)注5)の結合を介した凝集を誘導させると、KP-457を添加したiPS細胞由来の血小板では、ヒトから採血した血小板に劣らない高い反応性を示しました。さらに、この方法で作製した血小板を免疫不全マウスに輸血した後に、人工的に血管を傷つけて血栓を作らせた結果、KP-457を添加して作製した血小板では、より多くの血小板が集まって血栓形成に寄与することが確認されました。したがって、今回の方法で作製した血小板は、生体内においても機能性が向上していると考えられます。

Fig.3 KP-457存在下で作製したiPSC血小板のvWF/GPIbα依存的な凝集能の改善

Fig.4 KP-457存在下で作製したiPS細胞由来の血小板の生体内における血栓形成能の向上
通常の方法で作製したiPS細胞由来の血小板(上側)とKP-457を添加して作製した血小板(下側)。赤色:iPS細胞由来の血小板、緑色:血管、ピンク色:血栓の形成部位。
これまでに、臨床応用を想定して、iPS細胞から大量の血小板を作製することに成功していましたが、作製中に血小板の機能が低下するという課題がありました。本研究によって、KP-457を培養添加物として加えることで、GPIbαを保持し、実際に止血機能を有する血小板を作製することが可能になりました。今後、この製造方法を採用して、iPS細胞由来の血小板を用いた臨床試験に向けて、開発を加速していく予定です。
- 論文名
Selective inhibition of ADAM17 efficiently mediates glycoprotein Ibα retention during ex vivo generation of human induced pluripotent stem cell-derived platelets - ジャーナル名
Stem Cells Translational Medicine - 著者
Shinji Hirata1,2, Takahiko Murata2, Daisuke Suzuki1, Sou Nakamura1, Ryoko Jono-Ohnishi1, Hidenori Hirose1,3, Akira Sawaguchi4, Satoshi Nishimura5, Naoshi Sugimoto1, and Koji Eto1,6 - 著者の所属機関
- 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)
- 科研製薬株式会社
- 株式会社メガカリオン
- 宮崎大学医学部
- 自治医科大学分子病態治療研究センター
- 千葉大学大学院医学研究院
本研究は、下記機関より支援を受けて実施されました。
- AMED「再生医療の実現化ハイウェイ」
- AMED「再生医療実用化研究事業」
- AMED「iPS細胞研究中核拠点事業」
注1)血小板
止血に重要な役割を果たす核のない直径2~3μmの血液細胞で、巨核球から分離して作られる。
注2)GPIbα
血小板の持つ特徴的なタンパク質の一つで、血管傷害部位への接着や生体内での血小板の寿命に関与する。vWFの受容体。
注3)ADAM17
タンパク質を切断するメタロプロテアーゼという酵素群の一つ。37℃においてGPIbαなどのタンパク質を切断する。
注4)リストセチン
vWFとGPIbαの結合を促し、血小板を凝集させる試薬。
注5)vWF
血液中に流れるタンパク質で、GPIbαと結合して、血小板を血管の傷害部位に接着させる。






















