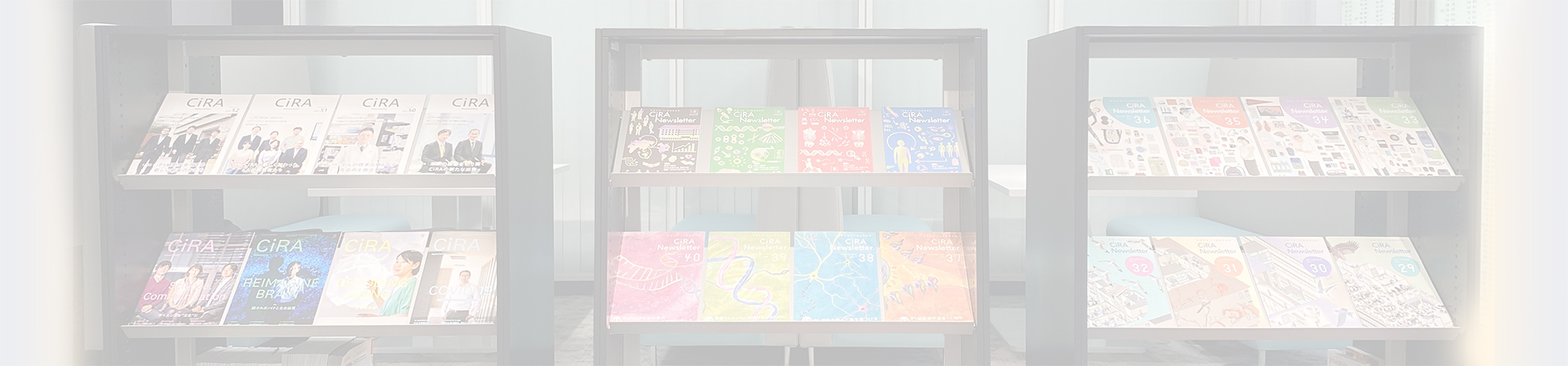
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

Focus
2024年6月17日
研究と子育ての両立 ~充実して働ける環境とは~ Vol.1
-育児支援のために意識を変えることがカギ-
ワークライフバランスは、働く人にとって重要なテーマです。特に子育てをする人にとっては、仕事と子育ての両立は大きな課題です。
京都大学でも、男女共同参画を積極的に推進しており、妊娠、出産、育児の各段階においてキャリアが継続できるよう、様々な支援策を実施しています。CiRAでは、相談窓口や女性休養室の設置のほか、人材の採用・育成・登用に潜む男女不平等などの「無意識のバイアス」を認識し、克服することの重要性に関する講演会も開催されました(※)。
そこで、研究と子育ての両立について焦点を当て、子育て中の3名の研究者に自身の経験や誰もが充実して働ける環境作りの課題についてインタビューしました。
第1回では、小田裕香子教授(京大大学院生命科学研究科教授/元CiRA准教授)にお話を伺いました。

小田裕香子教授
産休・育休は取得しましたか?
双子の娘がいまして、現在7歳、小学2年生です。産休は産前・産後2ヶ月ずつ、育休は5ヶ月取りました。娘たちの首がすわるまで育休を取ろうと決めていました。首がすわらないと、2人を保育園に連れて行くのは大変だと思ったからです。当時は助教という立場で、年度末にはさまざまな報告書の作成などがあるので、それまでに復帰したいと考えていました。復帰するにあたり、職場の先輩から保育園情報を事前に聞き準備を進めました。
産休・育休の取得は研究にどのような影響を与えましたか?
研究は確かに遅れましたが、「出産は自分が決めたこと。それを含めての自分の人生、自分の研究活動」と覚悟していたので、遅れたことで焦りは感じませんでした。それよりも、復帰後が大変でした。子どもが順番に病気になって、1人は病児保育室、もう1人は通常の保育園に連れて行ったりと、1年くらいはその繰り返しで労力がかかりました。私の親にも家事や育児を手伝ってもらいました。
育児と研究のバランスをどのように取っていますか?
出産前に比べて研究時間は短縮されていますが、優先順位を決めて効率的に取り組むよう工夫しています。保育園の送り迎えをしていた時は、研究の終わり時間が決まっていたので、できる限り集中して仕事をしていました。夫もできる範囲で協力してくれており、特に休日は夫が積極的に育児を担ってくれています。最近は2週間に1回、朝から晩まで丸1日夫に子どもの面倒を見てもらって、私は完全に自由の身になって研究や自分の用事をしています。
どのような支援が役立ちましたか?
毎日通う保育園に加え、京都市の病児保育サービス、京大の待機乳児保育室が非常に役立ちました。京都市のシルバー人材センターのサポートも利用しました。また、京大には「研究支援・実験補助者雇用制度」という育児・介護で研究時間の確保が困難な研究者のための補助者雇用経費を支援してくれる制度があり、このサポートは大きかったです。
あと、当時の上司だった豊島文子教授(京大医生物学研究所)が、妊娠・出産についてポジティブな言葉をかけてくださりずいぶん救われました。例えば、「妊娠したらホルモンバランスが変わって、研究のアイディアが色々出てくる」と言ってくださったり、ご自身の妊娠・出産の経験について明るく話をしてくださり、産休・育休を取って申し訳ないという気持ちが軽くなるような良い雰囲気を作ってくださったりしました。つわりで具合が悪い時も、自然に気遣ってくださいました。出産や育児をする人にとって、職場の雰囲気が良いことは重要だと思います。
子育て中の研究者にとって働きやすい職場環境を作るために、何が必要だと思いますか?
職場での育児支援は、制度のハード面と意識のソフト面と両方からのアプローチが必要だと思います。ハード面としては、研究も育児も頑張っている人が報われるような支援制度があればいいなと思います。ソフト面としては、出産・育児に対してみんなの意識を変えることが重要だと感じています。職場の雰囲気によっては、子どもを産むことを躊躇してしまったり、論文投稿や職探しが優先になって妊娠のタイミングを逃してしまうこともあるかと思います。そういうことが少なくなるような職場づくりが大切だと思います。

小田教授と生後6か月の頃の双子の娘
-
プロフィール: 小田 裕香子 教授
兵庫県出身。京都大学大学院理学研究科修了(理学博士)。神戸大学大学院医学研究科助教、京大医生物学研究所助教などを経て、2022年CiRA准教授、2024年より京大大学院生命科学研究科教授。細胞間接着を誘導するペプチドを発見し、その研究をもとに個体の恒常性維持などに取り組む。 -
取材・執筆した人:三宅 陽子
京都大学iPS細胞研究所 国際広報室 サイエンスコミュニケーター
※裏出令子京都大学名誉教授による講演「ダイバーシティを妨げる無意識のバイアスとは」の動画は、CiRA公式YouTubeでご覧いただけます。






















