
ニュース・イベント
News & Events
ニュース・イベント
News & Events
CiRAシンポジウム質疑応答
Q&A session
第5回 CiRA一般の方対象シンポジウム 第2部 Q&Aセッション
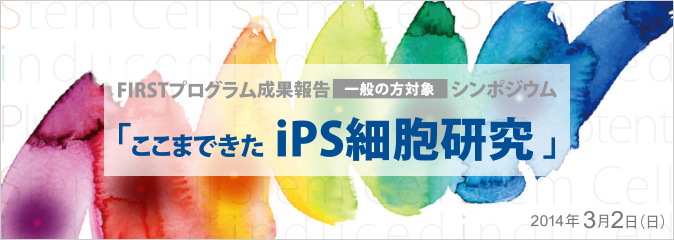
| パネリスト |
山中 伸弥 所長(山中と表記) 妻木 範行 教授(妻木と表記) 櫻井 英俊 講師(櫻井と表記) |
|---|---|
| 司会者 | 関根 友美さん(関根と表記) |
2014年3月2日(日)に開催された、CiRA一般の方対象シンポジウム「ここまできたiPS細胞研究」の質疑応答において、はじめに、参加者から事前に寄せられた質問を司会者から聞いていただき、パネリストが回答しています。残りの時間で、参加者が直接講演者に質問しました。以下の文章は、これらの質疑応答を要約したものです。
| 関根 |
これからのお時間は皆さまからの質問に対し、先生方にお答えいただきますQ&Aセッションとさせていただきます。まずは会場の皆さまからの質疑応答の前にシンポジウムお申し込みの際にいただいておりましたご質問の中から、お時間の関係で幾つか選ばせていただきました。まず山中先生にお答えいただきたい質問です。 |
|---|---|
| 山中 |
1型糖尿病はインスリンが治療に必須です。子どもさんが発症することが多いのですが、治療としてはインスリンを生涯にわたって1日に何度も、子供さんがご自身で注射をします。注射をすると血糖値は下がりますが、下がりすぎて低血糖発作で患者さんが倒れてしまったり、場合によっては命をなくしてしまったりすることもあります。治療も大変だし、副作用の低血糖発作が非常に大変という病気です。 |
| 関根 |
どうもありがとうございました。さまざまな道があるのだなと感じます。もちろん患者さんとして、ずっと闘病されていたそういう知見を生かして倫理とか法的なつながりとか、患者さんに向けた発信者とか、いろいろな道がありますよね、山中先生。 |
| 山中 |
本当にそのとおりです。 |
| 関根 |
続いては妻木先生にお答えいただく質問。 |
| 妻木 |
ありがとうございます。頑張ります。本日、私が話させていただきましたのは、軟骨が痛む、軟骨が原因で関節が悪くなる病態について説明させていただきました。関節リウマチといいますのは、自己免疫疾患の一つで、炎症が起こって、その結果、関節の軟骨が溶けてくるような病気です。その結果、全身の関節が悪くなって日常生活にも不便を来すような重症な疾患ですが、全身の炎症をコントロールすることが、ここ数年、生物学的製剤の開発によって可能になってきました。 |
| 関根 |
どうもありがとうございます。確実にステップを踏みながら、いずれはということですね。 |
| 櫻井 |
はい、ありがとうございます。ウールリッヒ型先天性筋ジストロフィーは確かにまれで、おそらく100人も患者さんはおられないと思います。生まれたときから筋力低下を呈して、将来的には呼吸もしにくくなるということで、かなり重篤な病気です。実際、iPS細胞研究で取り組んでおります。まだ患者さんからのiPS細胞ができていないので、いま難病研究をしている先生方にお願いをして、患者さんにiPS細胞をつくるということにご協力をいただけないかと研究班を通じて呼び掛けている段階です。幸いなことに実は申し出がありまして、極めて近い将来、ウールリッヒ型筋ジストロフィーの患者さんから細胞提供を受けてiPS細胞をつくらせていただきます。 |
| 関根 |
どうもありがとうございました。私は文系ですので、医学用語の難しいところになるとはあーと思うのですが、こんなことが発見されましたという、その熱みたいなもので、皆さん、本当に希望を持たれるだろうし、すごいスピードで進んでいるのだな、そうやって関係機関が手を結ぶことでこんなダイレクトな、ものすごくダイナミックなことが起きているのだなということを感じます。 |
| 参加者A |
献血によってホモドナーの方がいまたくさん見つかりつつあると言われたと思いますが、いま何人ぐらい見つかって、何パーセントぐらいカバーできる感じなのかを教えていただきたいのと、ES細胞研究はこの後消えてしまうのかというのがちょっと気になっています。お願いします。 |
| 関根 |
どうもありがとうございます。先ほど山中先生から、この会場にもしかしたら1人ぐらいホモドナーの方がいらっしゃるかもしれないと言われたので、どうやって献血したらいいのだろうと思われている方もいらっしゃると思うので、そこも含めて山中先生、お答えいただけますでしょうか。あとはES細胞研究がこれからどうなっていくのかについても、言及していただければ幸いです。 |
| 山中 |
まずホモドナーの方については、最初の5年は日本人の30%から最大50%ぐらいをカバーするのが目標です。最頻度の方で約20%カバーができますし、次の頻度の方を見つけると30%近くがカバーできます。いま私たちが探しているのは、一番頻度が多い方、2番目の方、そこくらいまでです。最頻度の方はもう何名も見つかっております。あとはiPS細胞をつくるのが、大変な手間暇がかかります。なぜかというと、普通の実験用ではなくて、移植用ですから、特殊なクリーンルームでつくる必要がございますし、つくった細胞を厳密に品質管理する必要もございます。すでに見つかってご協力の意思を示していただいているそういった方々から今後、まずしっかりしたiPS細胞をつくりたいと思っています。 |
| 関根 |
どうもありがとうございました。それでは引き続きましてご質問を受けたいと思います。 |
| 質問者B |
創薬と再生医療をやるためにiPS細胞をたくさんつくらなければならない。オールジャパンでやるためにも、供給というのが非常に大事だと思いますが、その場合、いまこの製造とストックをする組織は、どのような組織体を考えられているのか。例えば民間へ委託するのか、あるいは国営の企業みたいなものをつくって京大がコントロールしてやるような形なのか。世界にはiPS細胞やES細胞を供給するための組織的なものというのは、どんなものがあるのか。その辺をよかったら教えていただければと思いますが、よろしくお願いします。 |
| 関根 |
どうもありがとうございます。山中先生、お願いします。 |
| 山中 |
iPS細胞のストックもしくはバンクですが、再生医療用のものと創薬研究用のもので、二つに分けて考える必要があります。 |
| 関根 |
櫻井先生、いかがでしょうか。 |
| 櫻井 |
私に直結するところでは創薬用のiPS細胞バンクということですが、われわれが筋肉の病気の患者さんからつくったものを、日本では理化学研究所のバイオリソースセンターに寄託をして、そこからいろいろな研究者のところに分配し、皆さんに使っていただくという形で進めております。その事業が進めば、日本でも大きな創薬研究用のバンクができるのではと考えております。 |
| 関根 | それでは会場の皆さんから。 |
| 参加者C |
ご講演、ありがとうございました。先日新聞でiPS細胞の国際バンク的なものをつくりたいと山中教授がおっしゃっているというのを目にしましたが、それについての今後の展望をどのように考えているのか、お考えをお聞かせください。お願いします。 |
| 山中 |
日本人用の再生医療用のiPS細胞ストックは京都大学が中心になっていまつくっておりますが、イギリス、フランス、韓国、そういった国ではそれぞれの国の同じような計画があります。国によってHLAの分布が異なっていますので、いま私が一番期待しているのは、日本で140名のHLAホモの方を同定したiPSをつくると日本人の90%の方をカバーできますが、残りの10%の方、この方は日本人の中ではまれなHLAをお持ちの方です。この人たちにどうやって適合するiPS細胞をつくるか。日本では非常に少ない。しかし、ほかの国では非常に多いHLA型であることもよくあります。ですから、国際連携することによって、日本ではなかなか手に入らないけれども、フランス、もしくは韓国とか、そういう国では比較的たくさんおられて、日本人のまれなHLAをお持ちの方もカバーできる可能性があるのではないか、ということで国際協力が必要だと考えています。 |
| 関根 |
ありがとうございました。それでは一番前の2列目の方。 |
| 質問者D |
山中先生が最後のほう、4番目にお話しされましたALSですか、すごく関心を持ちました。神経の病気でいままで100年間ぐらい、いい治療が見つかっていないということですが、いま実際に苦しまれている患者さんたちがiPS細胞の今後の研究によって、実際に治療がうまくいくという見通しとしては何年後ぐらい、また、どれぐらいの研究の今後の見通しが計画でされているのでしょうか。教えてください。 |
| 山中 |
これはなかなか予想が難しいのです。薬の開発は製薬会社の場合でもたくさんの化合物のスクリーニングから始まって、本当の意味の臨床にいくまでは10年、20年という時間が簡単にかかってしまいます。ですから、iPS細胞を使った場合も、その薬が新たに開発する化合物、これまで薬として使われていないものがiPS細胞を使って有効だと分かった場合に、それを実際の臨床まで持っていくとなると、やはり10年ぐらいの時間は簡単にかかってしまいます。 |
| 関根 |
どうもご質問、ありがとうございます。妻木先生もさまざまな患者さんと向き合っておられるので、一刻も早くというプレッシャーであったりとか、いつになったらというのはいつもさらされておられるお悩みではないかと思いますが、ご自身の研究の中で何か感じられることはありますか。 |
| 妻木 |
今日お話しさせていただいた再生という面からは細胞を移植するということになりますので、そのときにやはり安全性ということが非常に大事になってきます。まずいわゆる非臨床試験という動物を用いた研究でしっかり有効性と安全性を見ていくというステップ。それから、次は臨床研究という、ごく少数の患者さんに対して行うものですね。そういうステップを踏んでいって、着実にやっていきたいと思いますが、一応、目標としましては、本日お話しさせていただきましたように7年以内に軟骨に関しては臨床研究を始めたいという目標は持っております。 |
| 関根 | それでは、質疑応答を続けたいと思います。 |
| 参加者E | 先日、新聞に出ていた癌における免疫療法でiPS細胞を使ってという記事を読みましたが、こちらの展望と可能性みたいなところをちょっと聞かせていただければと思います。 |
| 関根 | では、櫻井先生、お願いします。 |
| 櫻井 |
答えさせていただきます。免疫療法ですが、癌細胞は、実はわれわれの体の中に結構、日々できていて、それを自分の免疫細胞、外敵からやっつけるだけではなくて、癌になった細胞を早く見つけてやっつけるという細胞がわれわれの体の中に実はあります。これを使いますが、臨床応用として体の中から取りだしたものを増やしていくということは結構されていますが、培養が進んで増やしていく間にどんどん能力が落ちてしまう。若い免疫細胞をたくさん用意する必要があるということが分かってきました。 |
| 関根 |
どうもありがとうございます。それでは後ろのほうの方。 |
| 参加者F |
座ったままで失礼します。パーキンソン病になって19年目です。この間から聞いている話では治験のことについてお伺いしたいのですが、治験の場合、年が若いほうの人からやっていくということをちらっと聞いたのですが、それは本当でしょうか。 |
| 関根 |
どうもありがとうございます。先ほど報道されましたパーキンソン病の治療について、若い人から治験を受けているということですが、その辺りの実情のほうを3名の皆さんの中でどなたかお話しくださいますでしょうか。山中先生、お願いできますか。 |
| 山中 |
日本の場合、臨床試験は臨床研究と呼ばれるものと、治験という2段階があります。専門的な話で申し訳ありませんが、いま髙橋淳先生が数年以内に始めようと考えておられるのは臨床研究です。どういう患者さんをまずこの臨床研究にご協力いただくかというのは、いま髙橋先生のほうでほかのパーキンソン病のいろいろな専門の先生方と相談されていると思います。まだ決まっていないと思います。 |
| 関根 | どうもありがとうございます。それではお時間のほうが近づいてまいりましたので、最後に一つだけ質問を受け付けさせていただきます。 |
| 参加者G |
今日は鹿児島からまいりました。私の息子は3人子どもがいますが、1人がウィルソン病です。発見が少し遅れまして、ペニシラミンの治療が遅れまして、いま軟口蓋の麻痺で言語障害が非常に強いのです。 櫻井先生の中にPeriodic Paralysis、周期性四肢麻痺も治療対象に入っていたので、ウィルソン病も対象に入るのかどうか、ちょっとお聞きしたいのですが。 |
| 櫻井 |
周期性四肢麻痺がなぜ研究に入っているかというと、筋肉の表面のイオンチャネルという収縮のときに必要なタンパク質に変異があるということが分かっていますので、変異があると分かっている患者さんで筋肉をつくって評価する研究をしています。申し訳ありませんが、ウィルソン病は現在取り組んでおりません。 |
| 関根 |
どうもありがとうございました。今日は鹿児島からお越しくださったということで、本当にありがとうございます。 |
| 山中 |
たくさんのご質問をいただきまして本当にありがとうございます。本来、皆さまのご質問に一つ一つお答えしたいのですが、一部しかお答えできなかったことをおわび申し上げます。 しかし、私たちのiPS細胞研究所のホームページがございまして、そちらのほうにはよくいただく質問に対する答えを掲載しておりますので、そちらもぜひご覧いただけたらと思います。皆さん、本当にありがとうございました。 |






















