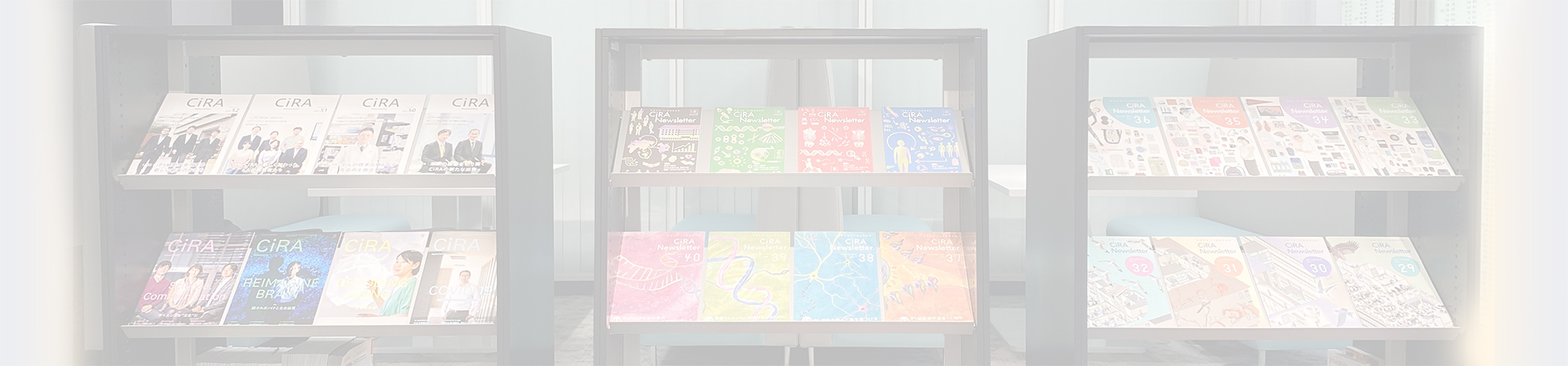
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

People
2023年4月21日
再生医療研究に取り組みながら、女性科学者を支援しメンタルヘルスについて啓発する

シャーロット・フラウ研究員
「私のこれまでのキャリアですね?」フラウさんはインタビューの席につくと、話し始めました。「ワクチンの研究をしてきました。企業で分析方法の開発や神経科学分野の研究に取り組んだこともあります。今はCiRAで再生医療の研究を行っています。とても幅広い分野ですが、多発性硬化症の研究に取り組みたいと考えています」
フラウさんは現在、江藤浩之研究室の研究員として働いています。年内には博士研究員として米国ボストンにあるハーバード大学医学大学院に移り、これまでに学んださまざまな知見を活かして、脳や脊髄などの中枢神経系に異常が起こる多発性硬化症に対する治療法を開発するという目標に向かって研究を始める予定です。
江藤教授の研究室では、主に血液の細胞を使用し、免疫反応がおこりにくい細胞を使った治療法の研究に取り組んできました。この研究によって、どのように免疫反応がおこるかを理解し、誰にでも輸血可能なiPS細胞由来の血液細胞の作製に結びつけることができるかもしれません。当初、フラウさんはヒト化マウスモデルを使い、免疫原性と呼ばれる生体内で免疫反応を引き起こす性質について検証を行っていました。ヒト化マウスとは、遺伝子工学の方法でマウスの遺伝子の一部を人間の遺伝子に置き換えたマウスです。これと並行して、iPS細胞由来血小板の自己か非自己かを判別するHLA(ヒト白血球抗原)発現が抑制されると、HLAがなくなることで起こる免疫防御システムが起こらなくなる原因も研究していました。
日本での生活については、「外国人に共通していることですが、日本では孤独だと感じます」と話します。新型コロナウイルス感染症の流行は、日本語がままならない多くの外国人にさらなる追い討ちをかけました。フラウさんも私生活や研究で困難に直面しました。コロナ禍で母国から離れて暮しながら博士号取得を目指すという不安な状況に置かれたフラウさんにとって、指導教官の江藤教授や、彼女自身が築いたサポートネットワークが大きな支えになり、とてもありがたかったそうです。このサポートネットワークのおかげで、気持ちの浮き沈みにうまく対処できたのです。
コロナ禍では、彼女の実験は中断を余儀なくされ、狭いマンンションに閉じこもる状況が続きました。その間、総説論文を書いたり、新しい論文を読んだりしていました。ボルダリングのジムに通えなくなり、自宅でヨガをするようになりました。ワークライフバランを保つためには、「趣味を続けることが大切です」とフラウさん。ストレスに晒らされ続けると創造性や生産性が損なわれるため、研究以外で自分を高めることが重要と言います。そして、フラウさんは子供の頃からの夢であったオペラを1年前から習い始めたと打ち明けて、こう言いました。「大きな声で歌うこともストレス発散になるんです!」

研究活動の他に、フラウさんは女性研究者による国際団体「500 Women Scientists (500WS)」や国内のメンタルヘルス支援グループ「TELL Japan」でボランティア活動をしています。ほとんど寝ていない、と冗談っぽく言いつつも、魅力的な赤毛のフラウさんは活き活きとしています。
彼女は来日直後に科学雑誌「Nature」の短い記事を読んで500WSのことを知り、日本で女性研究者とのつながりを探し始めました。残念なことに(同時に幸運でもあったのですが)、当時、500WS関西支部の活動は活発ではなく、新たな世話役を探していました。フラウさんと、知り合ったばかりの大阪大学助教のフィオナ・ルイさんが世話役を引き受け、女性研究者の相互支援を目的として月例ミーティングを開いて支部の活動を再開させました。
彼女らの努力により、2人だけのグループが学生から教授までさまざまな段階にある女性研究者30人の団体へと成長しました。メンバーは月に1回集まり、コーヒーやお菓子を食べながら、キャリアについて助言し合ったり、人間関係の問題や女性研究者が日々直面するストレスや不安に対処するために助け合ったりしています。
「助けを求めてほしい。一人で悩む必要はありません」日常生活や仕事場で困難に直面している人へのフラウさんからのアドバイスです。多くの人は、無気力になったり、落ち込んだり、不安になったりしても助けを求めず、自分を過小評価し、自信を失うインポスター症候群と呼ばれるような状態に陥ります。自分の状況を伝えて誰かに助けを求めれば、大変な状況にいるのは自分一人ではないことや、どんな問題にも解決策があることに気づくことができ、勇気づけられるのです。
フラウさん自身もコロナ禍を乗り越えるのに500WSの関西支部メンバーからの支えが不可欠でした。助けを必要としている人たちに、手を差し伸べてくれる人たちがいることを知ってほしいと話します。関西支部は外国人と日本人で構成されていますが、メンバーは英語を使って交流しています。なお、京都大学男女共同参画推進センターでは日本語で女子学生や研究者を支援しています。
研究、ボランティア、趣味の活動と忙しい日々を過ごしているフラウさんですが、リラックスタイムにすることは、CiRAから徒歩15分くらいにある出町柳駅近の「古都香」できなこ団子を食べることだそうで、「こんなに美味しいきなこ団子はありません。食べ始めたら止まりません」と笑顔で話します。もうすでにボストンでどんな研究をしようかと考えているようですが、彼女は果たしてアメリカできなこ団子に変わる好物を見つけられるのでしょうか?
(インタビュー後のフラウさんのコメント:「そうだなぁ、わかった!チーズケーキだと思う。きっと」)
-
取材・執筆した人:ケルビン・フイ
京都大学iPS細胞研究所(CiRA)
研究推進室 特定研究員(翻訳:CiRA国際広報室)






















