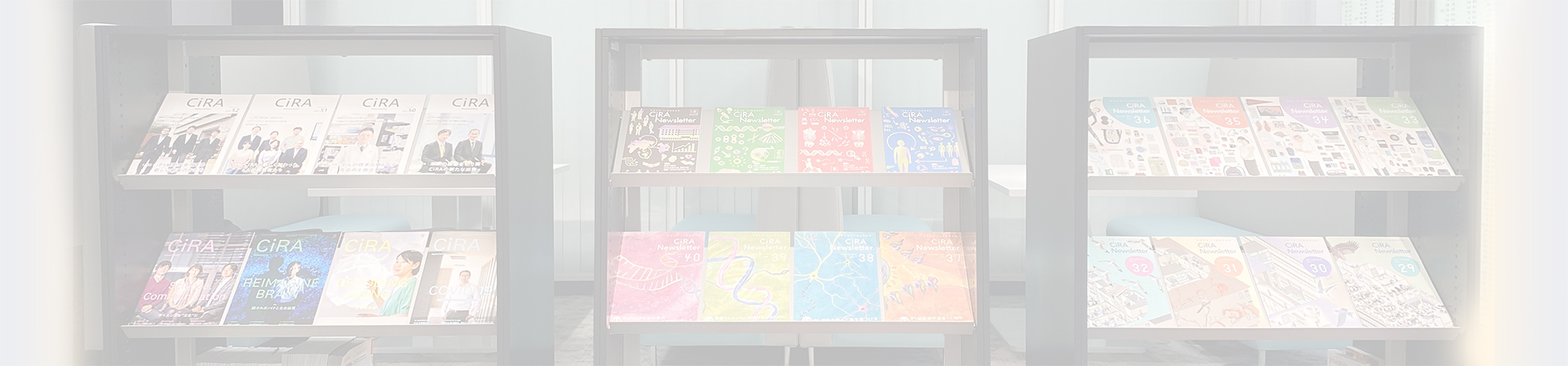
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

Focus
2024年6月20日
研究と子育ての両立 ~充実して働ける環境とは~ Vol.2
-私たちから始める快適な職場づくり-
研究と子育ての両立に焦点を当てたインタビューシリーズの第2回です。今回は、CiRAの高橋和利准教授に、アメリカと日本の違いや、育児中の人が快適に働くための職場づくりについてお話を伺いました。

高橋和利准教授
育休を取得しましたか?
子どもが2人いて、長男は10歳で小学5年生、長女は5歳で保育園に通っています。長男が0歳の時は、ちょうどCiRAで研究室を閉じてアメリカで研究を始める準備期間だったため、育休を取らずに時短勤務や年休を利用しました。その後、家族でアメリカに行き、4年間過ごしました。長男をアメリカで育てられたことは良い経験だったと思います。
長女は、妻が先に日本に返り出産しました。私は長女が産まれてから半年間はアメリカで単身赴任していました。帰国後すぐには仕事を始めずに2ヶ月ほどは育児に専念しました。長い時間子どもと過ごせて、本当に価値がある時間だったと思います。そういう状況でしたから、子どもが生まれた時に研究に支障を来すことはありませんでした。
育児と研究のバランスをどのように取っていますか?
子どもがいることで、仕事への向き合い方が大きく変わりました。仕事は代わりがいますが、子どもたちは私を必要としており代わりがいません。ですので、仕事をする上で、どうしてもやらないといけないことと、やらなくてもよいことを極端なぐらい取捨選択して、仕事を極力減らすようにしています。朝は6時に出勤して18時頃には帰宅し、晩ごはんをつくって子どもと食べたり、宿題をみたり、お風呂に入れたりしています。
妻も忙しく働いていますが、家事や育児の分担は特に決めていません。自然と役割が分かれており、それぞれができる範囲で協力してやっています。妻の両親が近くに住んでいますので、子どもが体調を壊してしまい夫婦共に休めない時など、どうしても困ったときは頼っています。そういう点では、恵まれていると思います。
子育てについて、アメリカと日本の違いは感じましたか?
アメリカに、日本にはないような特別な子育てのサポートがあったというわけではありませんでした。日本と同じく、アメリカでも保育園の数が足らず、みんな必死になって子どもを預ける場所を探していました。
日本と大きく違ったところは、アメリカで私たちが住んでいた地域は保育園に送り迎えにいくと、半分かそれ以上は父親が来ていました。今、日本で保育園に送り迎えに行くことがありますが、男性は私一人だけということがよくあります。それだけアメリカは女性が活躍しているし、「女性が子育てをするもの」という固定概念がないのだと思います。
職場での子育て支援について改善してほしい点はありますか?
私の研究室でも子育て中のラボメンバーがいます。小学校が夏休みのときに、ラボメンバーの1人がどうしても子どもを預けるところが見つけられないことがありました。私がCiRAの担当者に「おとなしく宿題をすることができるし、責任をもって面倒をみるので、数日間、研究室に子どもを連れて行ってもよいか」と問い合わせたところ、許可は得られませんでした。アメリカではそのような場合に子どもを職場に連れていっても、特に何も言われません。自己責任でやってくださいというスタンスです。CiRAはもう少しフレキシブルでもよいのではと思います。
CiRAが変わるのを待つだけでは仕方がないので、私の研究室から変えていき、子育て中の方に快適に働いてもらいたいと思っています。例えば、私が子どものために積極的に休むことで、ラボメンバーが子どものために休んでも「他人に迷惑をかけている」と感じさせないようにするなどです。私の研究室で始めた取り組みが他の研究室にも広がり、最終的には研究所全体の雰囲気が変わることを期待しています。

高橋准教授と生後4か月の頃の息子
-
プロフィール: 高橋 和利 准教授
広島県出身。奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科修了(バイオサイエンス博士)。CiRA講師、米国グラッドストーン研究所研究員などを経て、2022年よりCiRA准教授。未同定のタンパク質やRNAなどの分子に着目し、細胞の運命決定の謎を解き明かすことを目指す。趣味は路地探索、寄り道。 -
取材・執筆した人:三宅 陽子
京都大学iPS細胞研究所 国際広報室 サイエンスコミュニケーター






















