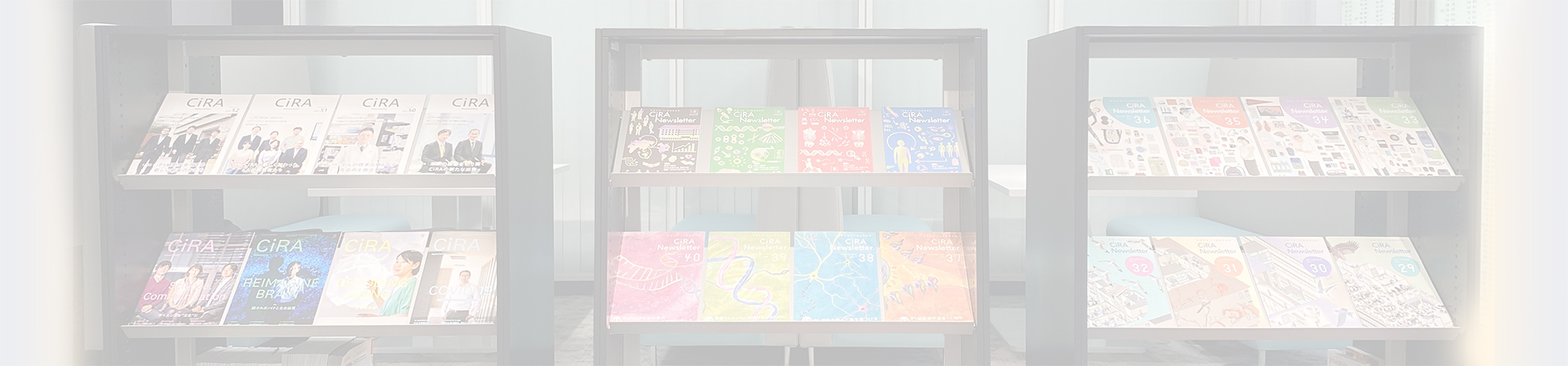
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

Focus
2024年6月21日
研究と子育ての両立 ~充実して働ける環境とは~ Vol.3
-夫婦のチームワークと保育施設の重要性-
研究と子育ての両立に焦点を当てたインタビューシリーズの第3回(最終回)です。今回は、CiRAのデニス・ズフル研究員(池谷真研究室)に、日本で暮らす外国人にとっての子育てや、働きやすい職場にするための課題についてお話を伺いました。

デニス・ズフル研究員
産休・育休は取得しましたか?
2歳の息子がいます。出産前に1ヶ月の産休と出産後に4ヶ月の産休・育休を取りました。息子はおそらく保育園で最年少の赤ちゃんだったと思います。私はサイエンスが大好きなので、どうしても早く研究に復帰したいと思っていました。
育児と研究のバランスをどのように取っていますか?
事前に計画を立てることと夫とのチームワークが重要です。夫も企業で研究者をしており、育児を分担しています。週単位、月単位で計画を立てますが、どちらかが出張がある場合はより綿密な事前の計画が必要です。研究を進めるために学会や会議への参加は不可欠ですが、調整は難しいです。特に海外出張の時は大変です。
私は裁量労働制で働いており、融通が利くのでとても助かっています。状況に応じて夫と育児の時間を調整しています。例えば、午前中は私が息子の世話をして、午後か夕方にCiRAに出勤してその日の仕事をしています。
徐々に仕事の効率的な進め方も分かってきましたし、どうしても時間的にできない実験はラボの技術員さんや学生さんに仕事の一部をお願いしています。周囲のサポートにはとても感謝しています。
どのような支援が役立ちましたか?
京大の「子の看護のための特別休暇」です。その休暇がないと、息子の看病のために有給休暇を使い切ってしまうところでした。子どもは突然病気になることが多いですし、日本にいる外国人の私たちは、いざというときに頼れる家族もおらず、親しい友人も少ないので、子の看護のための有給休暇があるのは素晴らしいことだと思います。
職場の子育て支援で改善してほしい点はありますか?
京大の学童保育所「KuSuKu」は土日と夏休みなどの長期休暇しか利用できません。京大で学んだり働いたりする親のために学内に保育施設を設置してほしいです。私は幸いにも息子を保育園に入れることができましたが、もし入れられなかったら、もっと長く育休を取る必要がありました。また、息子が小学校に入学したら、私の仕事が終わる前に授業が終わってしまうため、どうすればよいか悩んでいます。放課後に子どもの面倒を見てくれるような施設が学内にあれば、すごく助かると思います。
さらに、管理職者、特に男性の管理職者を対象にした、産前産後の女性への接し方についての教育プログラムも親や親になる予定のある人を支援することになるはずです。私は上司(池谷准教授)や同僚たちから大きなサポートがあったのでよかったですが、すべての人がそうではありません。何らかの教育プログラムがあれば理想的だと思います。
日本とベネズエラでの子育てに関する違いを教えてください。
私の母国ベネズエラでは、ほとんどの主要大学に、教職員や学生の子どもを預けられる保育施設があります。それに、大学側は、教職員や学生が放課後、週末、祝日に子どもを職場に連れくることに対してより好意的です。
日本では、長期の産休や育休がありますが、保育園を探す時から、多くの親は苦労します。フルタイムで働いている人や、近くに祖父母がいない人に限らず、利用する必要のある人なら誰でもが保育園を利用できるようにするべきだと思います。

ズフル研究員と夫と息子
-
プロフィール: デニス・ズフル研究員
ベネズエラ出身。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)。製薬会社を経て2020年よりCiRA特定研究員(池谷真研究室)。バイオテクノロジー関連のベンチャー企業の共同設立者でもあり、移植用の人工的な軟骨組織などを作製する革新的なツールを開発している。趣味は旅行、ネットワーキング、ダンス。 -
取材・執筆した人:ケルビン・フイ
京都大学iPS細胞研究所(CiRA)
研究推進室 特命講師(翻訳:国際広報室)






















