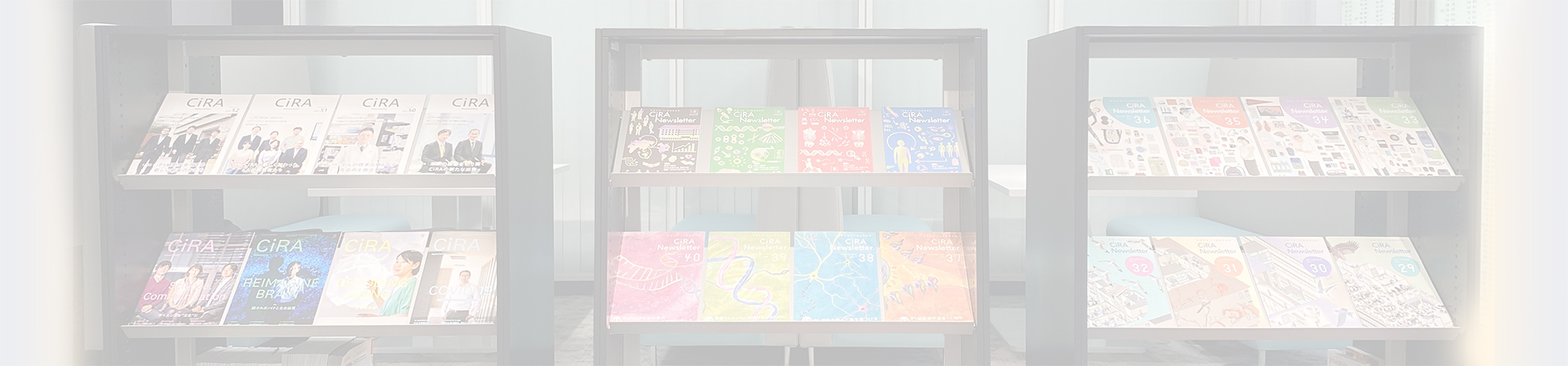
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

People
2025年7月1日
研究から医療への"橋渡し役"
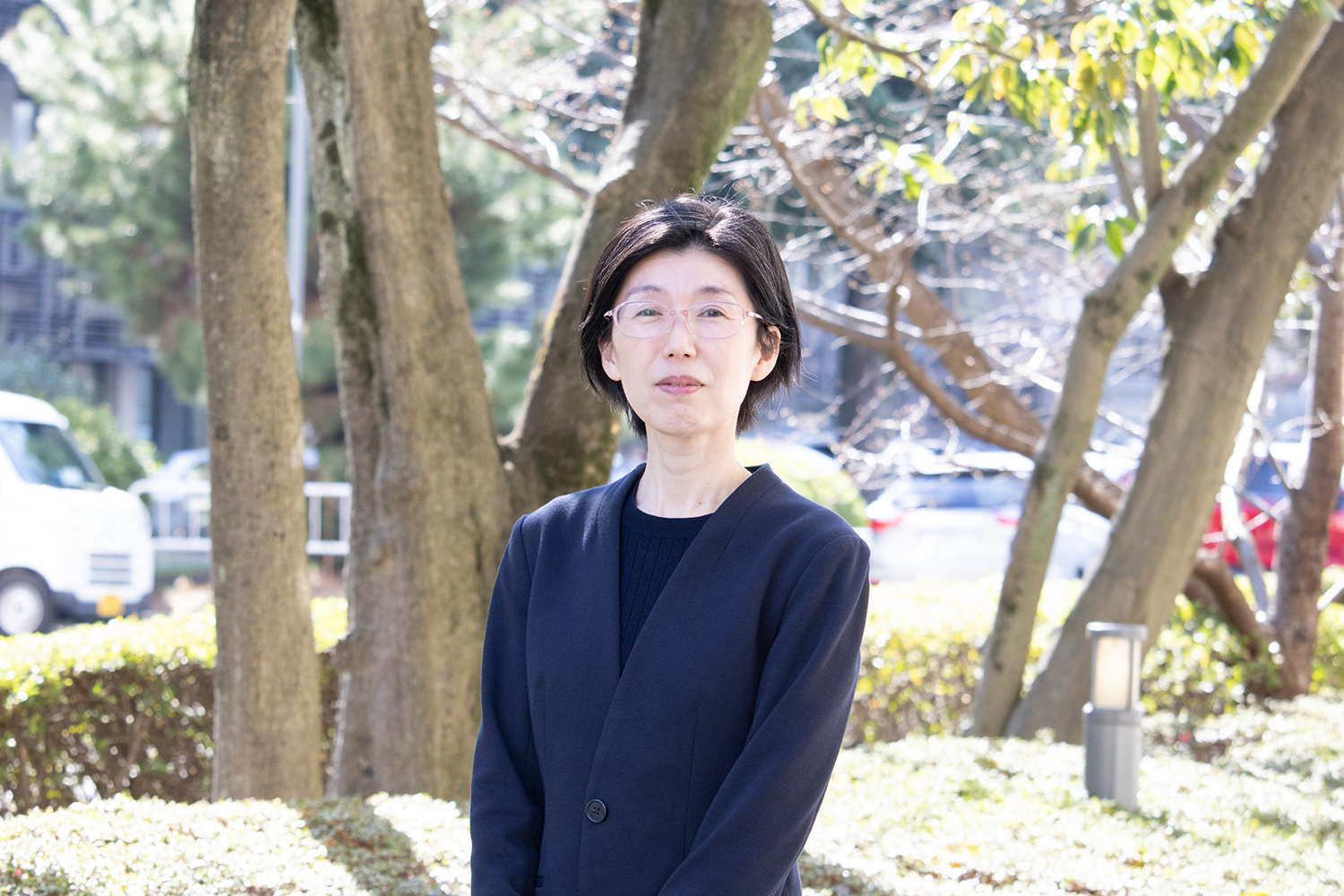
重政 亜紀子 さん
医療応用を実現するための支援
「基礎研究を医療応用へと進めるときに、法令や指針など遵守すべきルールがたくさんあります。その手続きを問題なく行い、研究プロジェクトを円滑に進められるよう支援するのが私の仕事です」と重政さんは語ります。
重政さんは、CiRAの研究成果を医療応用へとつなげるための研究計画に携わっています。研究計画を作成する際に、それぞれの臨床研究注1)に応じて適用される法令は異なるので、適切な制度やルールを見極めて対応することが求められます。また、再生医療研究となると前例のないケースも多く、非臨床試験注2)の計画・文書を作成するうえでも規制当局との相談が欠かせないと言います。
安全性確保のための調査
「細胞や薬などを初めて人に使うとき、予期しない健康被害が起きる可能性があります。最悪の場合、命に係わることもあり得ます。だからこそ、効果を確認する前に、まずは安全性をしっかりと確かめる必要があります。研究で使用していた材料が、人への移植や投与に使えるとは限りません」と重政さん。基礎研究から非臨床試験の段階になった際に、人間にとって安全な材料に変えなければなりません。その場合、同じ研究手法でも、材料を変えたときに本当にきちんとしたものができるか検証する必要があります。そのため重政さんは、必要に応じて材料の供給元と秘密保持契約を結び、材料の成分や製造方法などの調査を行います。
「調査は多くの労力を要します。ただ、これらの調査結果は今後、他の研究に応用できることもありますので、可能な範囲で所内の先生方にも情報を共有できればと考えています」

経験を活かしたサポート
重政さんがこの仕事に関わるようになったのは、2014年にCiRAの江藤浩之教授の研究室で技術員として働き始めたことがきっかけでした。血小板減少症の患者さんに対するiPS細胞由来血小板自家移植に関する臨床研究の準備に携わった経験が、現在の業務の基盤となっています。
「当時は、細胞の輸送も倫理申請もすべてが初めてのことばかりでした。手探りで進めたその経験が今の業務に大きく生きています」
また所内において、「医療応用を目指して研究を進めるうえで書類作成等の負担が大きく、サポートしてほしい」といった研究者の声が多く寄せられていました。こうした声に応える形で、研究計画支援グループが設立され、重政さんが着任することになりました。
やりがいとこれからの目標
重政さんの仕事は、CiRA倫理審査委員会事務局を含む他部署と連携し、スムーズな調整を図ることも求められます。どれか一つの手続きが進んでも、他の準備が整っていなければ研究は進みません。「全体がかみ合って『うまくいったね』と言いあえる瞬間が一番嬉しいですね」と重政さん。
発足からまだ3年目のグループですが、現在では多くの研究者が頼りにしています。「先生方にヒアリングすると、いろんな要望が出てくるんですね。なので、やれる範囲で提供できるサービスを拡充していきたいです。医療応用に関わる相談に限らず、一度関わった先生からまた相談してもらえるような、そんな存在でありたいと思っています」と重政さんは話します。
CiRAにおける基礎研究から医療応用への“橋渡し役”として、研究計画支援グループの活動は今後も進化を続けていきます。
注1)臨床研究
人を対象として行う医学研究。病気の原因を探ったり、新しい治療法や薬の効果・安全性を調べたりする。
注2)非臨床試験
人を対象とせず薬などの有効性、安全性、毒性などを調べる試験。
-
取材・執筆した人:三宅 陽子
京都大学iPS細胞研究所(CiRA) 国際広報室 サイエンスコミュニケーター






















