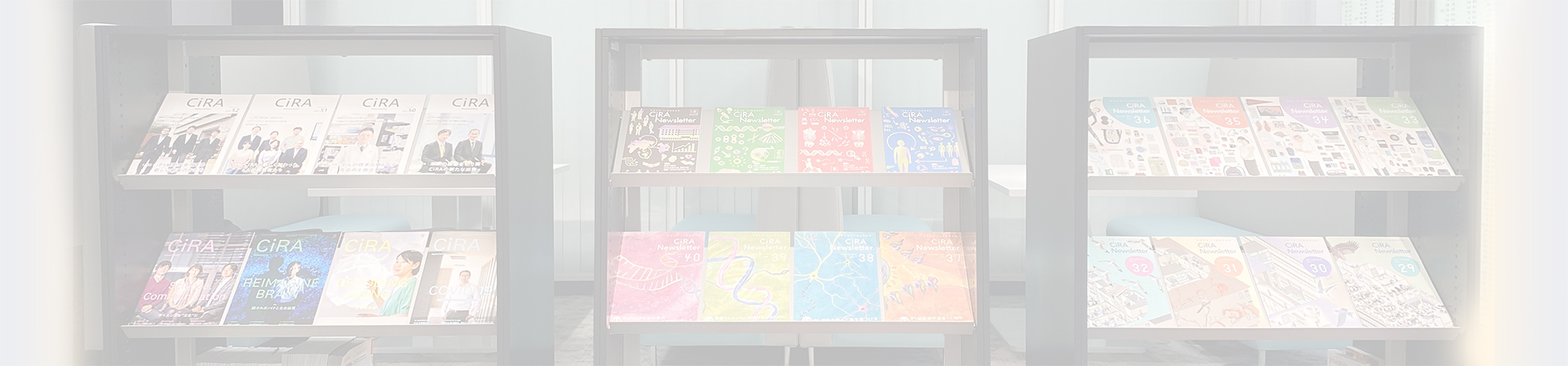
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

Ethics
2025年7月3日
倫藝:専門知と日常知との接続にむけて
好きな画家の一人に佐野ぬいさんがいます。佐野さんは作品制作において青色に思い入れがあり、作品上の独自の青色は「nuit blue」*1とも呼ばれています。この写真は、青森県の弘前市民会館(設計 前川國男)内のステンドグラス*2を撮影したものです。2014年に開館50周年を記念して制作されたもので佐野さんの原画が元になっています。
青色の作品といえば、私には画家のnakabanさんも思い浮かびます。nakabanさんとは幸運にも一緒にお仕事をする機会に恵まれました。私が生命観や技術観、歴史観等を取り扱う「生命倫理」という学術領域を論文や教科書、専門書以外の形態でも表現したいとお願いしたことがきっかけです。最終的に絵本『トラタのりんご』(制作 nakaban, 企画 三成寿作, 岩波書店, 2023年)の刊行にいたりました。「りんご」を主題として扱っていますが、日常で販売されているものとのつながりや種の系譜へのまなざし、生命や知恵、重力の象徴としての見立て等、自由に想像を膨らましていただけたらと思っています。
ところで、2025年は「民藝」という言葉が作られて100年の節目で、各地で企画展が開催されています。民藝は日々の暮らしの中の品々、ひいては日常における「美」や「楽しみ」の享受に重きをおいているように思います。また暮らしのあり方という点で民藝は生命倫理とも深く関係するように感じられます。私の中で生命倫理とは、人の生や死、日々の暮らし、社会、自然を通じた、望ましい、もしくは、再考すべき価値のあり方への探究を指します。この概念は、専門的な知識や経験においてのみならず、必要なものが足りない、もしくは余っている場合の対応、時間のない時やある時の振舞い等といった日常生活においても見出せるように思います。今、私が目指しているものは、専門知と日常知といった境界を越えた生命倫理をめぐる思索や技術、端的には「倫藝」とも表現できるかもしれません。
専門知と日常知との接続にむけて、昨年度は、CiRAで小・中学生を対象としたワークショップ『細胞について想像してみよう!』*3を企画・開催しました。本年度は、日本デザインセンターによって制作された、生命倫理に関する動画を木津川市情報発信基地キチキチ(京都府木津川市)において6月末まで(その後は「木津川アート2025」の期間中(9月下旬~10月上旬)に)展示する予定です。木津川市にお越しの際はご訪問いただければ幸いです。

作品「青の時間」
(原画作家 佐野ぬい, 企画 日本交通文化協会)
*1 nuitはフランス語での夜の意味であり、ご自身の名前の「ぬい」との掛け合わせで作品へのサインとしても使用されていたそうです。
*2 弘前市民会館「青の時間」
*3 京都市青少年科学センターが主催する「未来のサイエンティスト養成事業」の一環。本ワークショップでは、クリエイティブ・ユニット tupera tupera(ツペラ ツペラ)さんの協力により制作された作品「曖昧で確かなもの」を用いました。本作品はCiRAの一階に展示しています。























