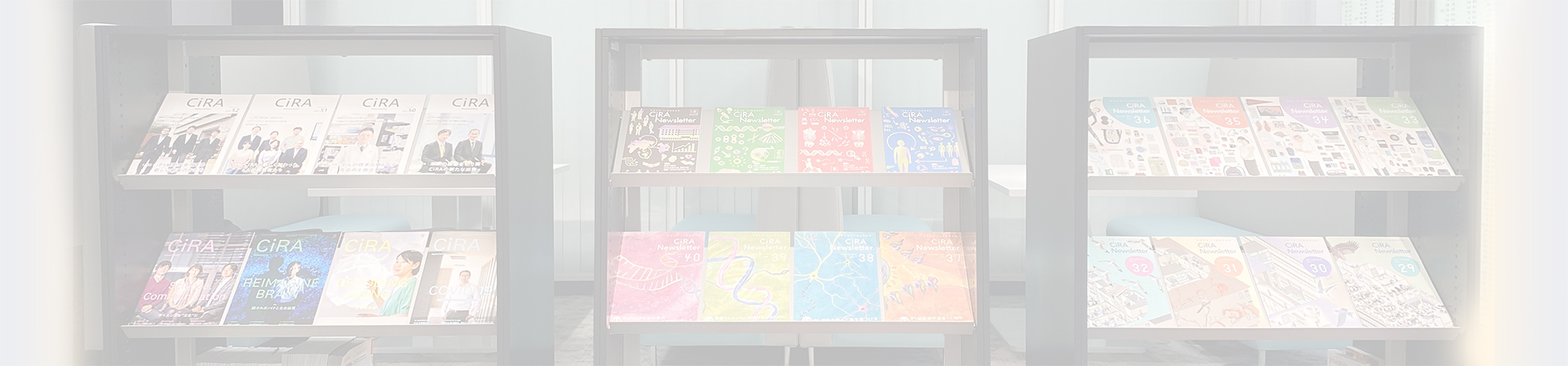
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

Focus
2025年10月14日
CiRAの研究者・学生116人に聞きました!
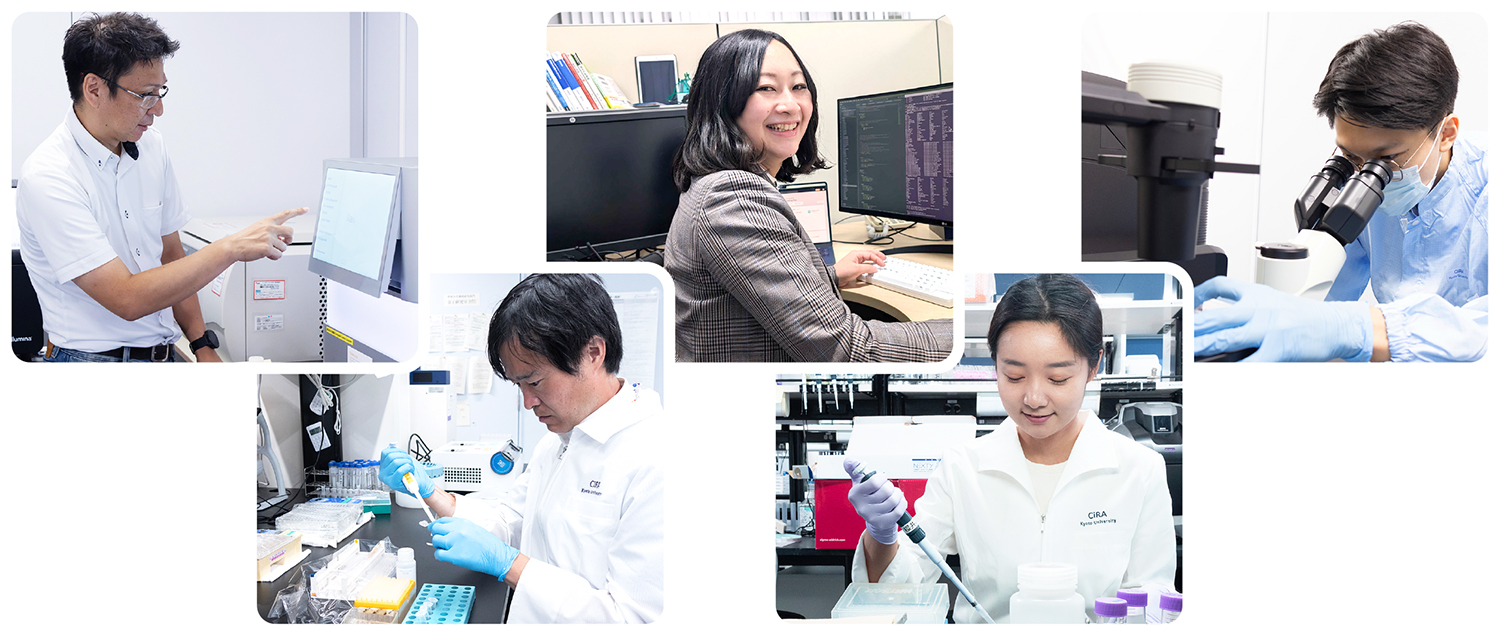
CiRAで日々研究に励む研究者や学生たちは、どのような思いで研究に取り組んでいるのでしょうか。今回、研究者・学生を対象にアンケートを実施し(2025年7月22日~8月1日)、対象とした297名中、研究者(教員・研究員)73名、大学院生など43名、計116名から回答を得ました。CiRAで研究しようと思った理由、研究のやりがいと苦労、そしてCiRAの魅力や今後の課題などについて率直な声を集めました。このアンケート結果と回答者5名のインタビューから、研究者・学生のリアルな姿の一端や研究への熱意を感じていただけたらと思います。
回答者の基本情報
出身学部も出身地域もこんなにいろいろ!
CiRAで研究する人と聞くと、「医学部出身ばかり」と思われる方もいるかもしれません。実際には、出身学部・学科は多様で、それぞれの専門性を持ち寄って研究を進めています。出身地域も幅広く、日本各地、そしていろいろな国・地域から研究者や学生が集まっています。「CiRAでは他分野の研究者と交流や共同研究ができる点が魅力です」というアンケートのコメントもあり、多彩なバックグラウンドの人々が交わることで、新しい発想や研究の広がりが生まれていることがうかがえます。
CiRAで研究したいと思った理由は?
アンケートで選んだ選択肢について、選択理由を尋ねたところ、研究者・学生ともに、iPS細胞を使って「基礎研究をしたい」「臨床応用を目指していた」「創薬研究を行いたかった」といった声が多く寄せられました。新しい治療を生み出したいという思いが、CiRAを選んだ理由の一つとなっています。また、研究設備や研究費の充実といった研究環境の良さも決め手になっていることがわかりました。学生は、「教員に魅力を感じたのが一番の決め手」「同じ女性としてロールモデルになりうる女性PI(主任研究者)の指導を受けたかった」など教員に関する回答が多く見られました。
iPS細胞を用いた再生医療は病気を治す大きな可能性を持っています。金子研究室はiPS細胞を用いた免疫細胞によるがん治療の研究を進めており、すでに一部は臨床試験段階に入っています。私もがん患者さんの役に立つことで社会貢献をしたいという思いから、CiRAに入ることを決めました。患者さんに使える治療を開発するためには、多くの課題があり大きな労力が必要です。それでも「患者さんに役立つ治療法を生み出す」という目標こそが、私にとって大きな原動力になっています。
iPS細胞を用いた再生医療は病気を治す大きな可能性を持っています。金子研究室はiPS細胞を用いた免疫細胞によるがん治療の研究を進めており、すでに一部は臨床試験段階に入っています。私もがん患者さんの役に立つことで社会貢献をしたいという思いから、CiRAに入ることを決めました。患者さんに使える治療を開発するためには、多くの課題があり大きな労力が必要です。それでも「患者さんに役立つ治療法を生み出す」という目標こそが、私にとって大きな原動力になっています。
研究をしていて面白さややりがいを感じるときはどのようなとき?
研究者・学生ともに最も多かったのは「新しい発見に出会えた時のうれしさ」です。失敗を重ねた後に成果が得られたときの達成感や、予想外の面白い結果が出たときのワクワク感が大きなモチベーションになっています。「自分の発見が社会に貢献できるかもしれないと実感したとき」や「議論や交流から新しいアイデアが生まれたとき」との声も多く寄せられました。また、学生からは 「新しい実験手技を習得できたとき」など、自分の成長もモチベーションになっています。
新しいことを発見した時、とりわけ予想外の発見が新たな知見につながった時に、研究は非常に面白く、刺激的に感じます。かつての指導教員が「研究で何かを発見した時、それはあなたが世界で最初に知ったことかもしれない」と言ってくれた言葉に大いに励まされました。また、自分の研究が将来、臨床に応用される可能性があることも、大きなモチベーションになっています。特に、今年の5月からCiRAという臨床応用の最先端の環境に身を置くことができ、その思いを一層強くしています。
新しいことを発見した時、とりわけ予想外の発見が新たな知見につながった時に、研究は非常に面白く、刺激的に感じます。かつての指導教員が「研究で何かを発見した時、それはあなたが世界で最初に知ったことかもしれない」と言ってくれた言葉に大いに励まされました。また、自分の研究が将来、臨床に応用される可能性があることも、大きなモチベーションになっています。特に、今年の5月からCiRAという臨床応用の最先端の環境に身を置くことができ、その思いを一層強くしています。
研究をしていて大変だと感じることは?
研究者から多く挙がった声は、「長期的にサポートしてくれる研究費が少ない」など研究費に関する不安です。また、研究以外の事務的な業務の負担が大きい中で、「成果をコンスタントに出さないといけない」というプレッシャーを強く感じていることもうかがえました。雇用や給与などの待遇が不十分とのコメントも多数ありました。一方、学生は、「実験が思うように進まない」など、研究や実験の進展に関する悩みが最も多かったです。
研究者はそれぞれがフリーランス(自営業)のようなもので、これから何を研究するか、誰と一緒に研究するか、研究結果をどう社会に還元するか、研究資金をどう確保するかまで、すべて自分で方向を決め、責任を持つ必要があります。ワークライフバランスもその一つで、家事や子育てにどれだけ充てるか、研究にどれだけの時間や労力を割くか自身で考え、研究成果を上げていかなければなりません。一方で、自分が本当に興味をもつ研究プロジェクトに全力で打ち込めるのも研究者の醍醐味です。成果が形になったときの喜びは何にも代えがたいものがあります。
研究者はそれぞれがフリーランス(自営業)のようなもので、これから何を研究するか、誰と一緒に研究するか、研究結果をどう社会に還元するか、研究資金をどう確保するかまで、すべて自分で方向を決め、責任を持つ必要があります。ワークライフバランスもその一つで、家事や子育てにどれだけ充てるか、研究にどれだけの時間や労力を割くか自身で考え、研究成果を上げていかなければなりません。一方で、自分が本当に興味をもつ研究プロジェクトに全力で打ち込めるのも研究者の醍醐味です。成果が形になったときの喜びは何にも代えがたいものがあります。
CiRAで研究していて良いと思うところは?
※アンケート回答で多く出てきた言葉ほど
大きく表示される図(ワードクラウド)です。
「研究環境が整っている」「機器が揃っている」など、設備面への高い評価が圧倒的に多く寄せられました。最先端の機器や施設の充実は、CiRAの大きな強みといえます。次いで、「他分野の研究者と交流できて意見をもらえるところ」「優秀な研究者と議論できる」といった研究交流の魅力を挙げる声も目立ちました。さらに、「研究費や支援体制が充実している」といった研究支援や、「風通しが良い」「交流イベントがある」といった研究所全体の雰囲気に関する好意的な声も寄せられました。
CiRAには、さまざまなバックグラウンドを持つ人と気軽に交流できる環境があります。私の専門は細胞生物学ですが、臨床医の方や情報学・プログラミングに精通した方など、全く異なる分野の研究者が集まっており、多様な視点に触れられることは非常に価値があると感じています。また、CiRAの設備は充実しており、共通機器室のサポートも大変助かっています。例えば、使ったことのない機器でも、共通機器室のスタッフが丁寧にサポートしてくれるので、新しい解析にも気軽に挑戦できます。その結果、解析に対するハードルが下がり、「初めての実験でも専門家が助けてくれる」という心理的な安心感が生まれます。そのため、自分の専門外の領域にも積極的に取り組める環境が整っていると感じています。
CiRAには、さまざまなバックグラウンドを持つ人と気軽に交流できる環境があります。私の専門は細胞生物学ですが、臨床医の方や情報学・プログラミングに精通した方など、全く異なる分野の研究者が集まっており、多様な視点に触れられることは非常に価値があると感じています。また、CiRAの設備は充実しており、共通機器室のサポートも大変助かっています。例えば、使ったことのない機器でも、共通機器室のスタッフが丁寧にサポートしてくれるので、新しい解析にも気軽に挑戦できます。その結果、解析に対するハードルが下がり、「初めての実験でも専門家が助けてくれる」という心理的な安心感が生まれます。そのため、自分の専門外の領域にも積極的に取り組める環境が整っていると感じています。
CiRAの課題と感じているところは?
「研究室間の交流が十分でない」という声が最も多く寄せられました。日常的なやり取りは限定的で、「コラボレーションや情報交換のチャンスを活かしきれていない」といった課題が指摘されています。「海外のラボのように気軽なセミナーや交流会を開き、食事をしながら研究を議論できる場があればよい」「研究室同士のイベントがあってもよいのでは」といった具体的な改善提案も見られました。前述の質問項目では、研究交流の機会に高い評価をした回答者もいますが、まだ十分とは言えないようです。
次いで、「若手人材の育成があまり進んでいない」「学生へのサポートが薄い」といった意見も目立ち、次世代の研究者を育成するための制度や環境づくりが必要と考えられます。また、「一層の国際化が求められている」「研究の裾野を拡大すべき」といった意見も一定数ありました。iPS細胞研究をさらに推進しつつ、海外から人材を獲得する取り組みや新しい分野へ挑戦する姿勢が求められていると言えます。
CiRAの研究支援者の待遇改善は進められていますが、全体としては依然十分とは言えず、さらなる向上が必要だと考えます。例えば、高度な情報解析やプログラミングのスキルを持つ人材は、企業の待遇の方が良いため、大学や研究所では確保が難しい状況にあります。しかし、このような人材は現代の医学・生物学分野の研究推進に極めて重要です。そのため、給与面にとどまらず、働きやすい環境や柔軟な働き方も含めて、総合的に魅力ある職場づくりを進める必要があります。待遇改善は、優れた研究支援者の確保だけでなく、次世代を担う若手人材の参入にもつながると考えています。
CiRAの研究支援者の待遇改善は進められていますが、全体としては依然十分とは言えず、さらなる向上が必要だと考えます。例えば、高度な情報解析やプログラミングのスキルを持つ人材は、企業の待遇の方が良いため、大学や研究所では確保が難しい状況にあります。しかし、このような人材は現代の医学・生物学分野の研究推進に極めて重要です。そのため、給与面にとどまらず、働きやすい環境や柔軟な働き方も含めて、総合的に魅力ある職場づくりを進める必要があります。待遇改善は、優れた研究支援者の確保だけでなく、次世代を担う若手人材の参入にもつながると考えています。
将来をどう考えている?
子どもの頃に興味があったこと、中高生・大学生時代に特に力を入れた点は?
子どもの頃は自然や生き物、スポーツへの関心が強く、中高生時代は部活動や勉強に励んだ人が多いようです。大学で科学の面白さに触れ、研究者の道へ進んだとの声も目立ちました。
趣味やリフレッシュ方法は?
最も多く挙がったのは、体を動かすことでした。ランニングやウォーキング、水泳、筋トレ、テニスなど、さまざまな運動を楽しむ声が目立ちました。次に多かったのは、音楽に関する趣味です。コーラスをする人やピアノやギターを演奏する人、音楽鑑賞やコンサートを楽しむ人も多くいました。また、「研究自体が楽しみ」「研究について話すこと」など、研究が趣味という声もありました。
CiRAで研究したい人へのメッセージ(求められるスキルや研究の心構えなどはどんなこと?)
最も多かったメッセージは「好奇心を持つことの大切さ」でした。探究心や興味を持つ姿勢こそが、研究を大きく前進させる力になるようです。次に、「一番大切なのは、アイデア」というメッセージも多かったです。世界で初めてのことを発見するためには、独自の発想や切り口が欠かせないようです。「研究は長距離走のようなものなので、モチベーションや継続力が大切」や「国際的な場で活躍できるように、しっかり英語を身につけましょう」という声も一定数ありました。
メッセージ抜粋:
- 研究者として成功するためには、好奇心、創造性、問題解決能力、粘り強さ、コミュニケーション能力など様々な能力が高い次元で求められます。また、良きメンターや研究環境との出会いも欠かせません。もしCiRAの研究内容に興味を持たれたら、まずは一歩を踏み出してみて下さい。研究者になる夢を是非、叶えてもらえればと思います。
- モチベーションを維持することが最も重要なので、これを成し遂げたいと思う心を大切にしてください。
- 研究はうまくいかないことの方が多いですが、最終的にはポジティブに物事を考えるスキルが大事だと思います。まずは、やってみよう!という気概で何事も挑戦してみてください。
- 特別な技術は不要で、どれだけ熱意を持って取り組めるかが大事だと思います。
- iPS細胞研究は成果をまとめるのに時間がかかるので、粘り強く研究に取り組める忍耐が重要かも。実験が思い通りにいかない時こそ踏ん張り時です。
- 一番大切なのは、アイデア。そのアイデアを実現するために何が必要か、何をすべきか、自分で考えて、自分でやりきる自主性が重要。
- 分野や国籍を超えたコミュニケーション力と、CiRAが目指す未来に貢献できるような研究を行うことが大事だと考えています。
- 医療の未来を変えることができる研究だと思います。自らの研究の先に患者の未来を描いてほしいです。
※ワードクラウドは、ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析を使用し、CiRA国際広報室が作成しました。
-
調査・取材・執筆した人:三宅 陽子
京都大学iPS細胞研究所(CiRA) 国際広報室 サイエンスコミュニケーター



























