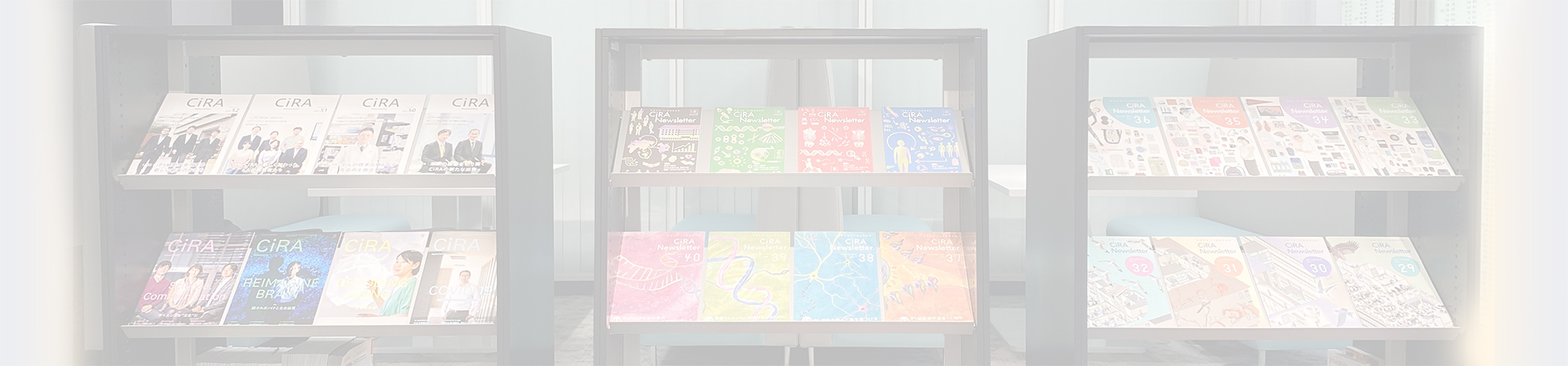
ニュースレター
Newsletter
ニュースレター
Newsletter

Internship
2025年9月30日
2025年度【第2回】CiRA研究インターンシッププログラム 成果発表会
2025年8月20日、CiRA講堂にて、CiRA研究インターンシッププログラムの第2回成果発表会が開催されました。
多様な研究部門からの、学びの共有
今回は5名の学生が発表し、プログラミング技術、再生医療と疾患のメカニズムの解明、そして倫理問題への取り組みなど、iPS細胞に関わる幅広いテーマの研究成果が報告されました。参加したCiRAの研究者や学生にとっても、新鮮な学術交流の機会となったのではないでしょうか。

第2回インターンシップ発表会に参加する
CiRAメンバー
口頭発表

二上麻央さん
東北大学農学部3年生で生物学と化学を専攻する二上麻央さんは、「パソコンを使ってデータ解析をする経験をしたい」という思いから、河口理紗研究室(未来生命科学開拓部門)において、1週間のインターンシップを経験しました。同研究室では、情報科学・統計・数理・機械学習といった学際的技術を利用して生命科学データの大規模比較解析のための手法開発を行っています。
iPS細胞の集団を観察すると、形成期やプライム期など、成長状態の異なる細胞が複数同時に存在していることがわかります。この1つの集団内における各成長状態の割合は、細胞の集団ごとに変わります。二上さんは、この割合を制御している要因について研究された既存の論文と、公開されている解析コードを参考に、R言語※1)を用いたiPS細胞の制御ネットワーク※2)モジュールを作成し、その解析結果を報告しました。
質疑応答で、二上さんの今後の予定について尋ねられると、「プログラミングができれば、様々な生物の遺伝子制御ネットワークモジュールを調べることができます。今回のインターンのおかげで、本来自分の専門では扱うことのなかった分野に触れることができました。自身の研究の幅を広げるためにも、引き続き自分で学習を継続していきたいです」と笑顔で答えました。

植田真実さん
続いて、東京科学大学医学部保健衛生学科3年生の植田真実さんが口頭発表を行いました。植田さんは、同大学の消化器系専門の研究室において、iPS細胞を肝臓に分化させる手技を学びました。また、拡張型心筋症という疾患を学ぶ機会を通じて心臓の再生医療に強く興味を持ったことから、今回、吉田善紀研究室(増殖分化機構研究部門)でのインターンシップを希望しました。吉田研究室では、心血管系疾患に対してES/iPS細胞を用いて再生医療、創薬、疾患メカニズムの解明を目標として研究を行っています。
iPS細胞由来の心筋細胞を臨床応用するために解決すべき課題の一つが、作製した心筋細胞の自動能※3)の抑制です。植田さんは、自動能を調節している要因に着目し、そのひとつと考えられているHCN4※4)をノックアウト※5)したiPS細胞由来の心筋細胞を作製して比較検討実験を行い、3週間にわたる研究成果を発表しました。
植田さんは「iPS細胞からできた心筋細胞が拍動するところを見た時は、大きな感動がありました。また、研究だけに集中して取り組める時間と、初めて自分で一つの研究を組み立てるというとても大きな経験を得ることができました。」と、インターンシップでの貴重な体験について振り返りました。

Rui Xiaoさん
最後の口頭発表は、河口理紗研究室(未来生命科学開拓部門)で4週間のインターンシップを経験した、中国華南理工大学化学・化工学部薬工学専攻3年生のRui Xiaoさんによる研究成果報告でした。
「副専攻はコンピューターサイエンスで、計算科学的手法やモデリングによって生化学的問題を解決することが得意です」と話すXiaoさん。生物学とその進化に機械学習を適応させたEVO2※6)というDNA基盤モデルに対して、幹細胞に特異的なシス制御エレメント※7)に関する学習能力の性能評価を行いました。
Xiaoさんは、EVO2が効率的に対象を捕捉しているかを評価するために、シス制御エレメントに特化した代表的なベンチマークのDNA言語モデルであるDART-Evalを用いました。そして各タスクにおけるEVO2のゼロショット性能※8)を、既存のDNA基盤モデル群と比較し、複雑な生物学的ネットワークの解読におけるEVO2の有用性に関する知見を報告しました。
Xiaoさんは、「中国では、ByteDanceやAlibabaといった大手IT企業が、AIや深層学習技術を活用して生物学的課題に取り組む専門チームを設けています。将来的には、このような分野で活躍したいと考えています」と今後の希望について語りました。
ポスター発表

森めぐみさん
東京藝術大学美術研究科博士後期課程1年生の森めぐみさんは、学部で作曲技法を学んだ後、楽曲提供や舞踊表現、難聴学級でのワークショップを通じて、東京藝術大学がすすめる「文化的処方」に関する研究に取り組んできました。
森さんが、三成寿作准教授(上廣倫理研究部門)が近年実践されている研究の内容、具体的には、科学とアートのコラボレーション企画の紹介記事や、対話型鑑賞に関する活動が掲載されている書籍※9)を読んだことがきっかけとなり、三成研究室において6週間のインターンシップを経験することになりました。
インターンシップの期間中には、「アートを介したPPI(患者・市民参画)とアーティストの役割について」というタイトルで研究成果を報告しました。
PPI(患者・市民参画)とは、AMED(日本医療研究開発機構)のウェブサイトでは、「医学研究・臨床試験のプロセスの一環として、研究者が患者・市民の知見を参考にすること」と紹介されています。そして、このPPIでは、研究者と患者・市民がパートナーとして連携していくことが重視されています。
森さんは、オランダの精神医療センター(アルトレヒト病院)で行われたアーティスト・イン・レジデンス(アーティスト滞在型のプロジェクト)を運営する「The Fifth Season」や、アートを用いた社会的課題への対策に資するワークショップといった事例を紹介しながら、アーティストが「外部者」として場に参入する際の障壁や課題、可能性について発表しました。
森さんは「インターンシップでは、CiRAに集まるさまざまな研究者、職員の方々と直接交流できたことで多様な視点に触れられる貴重な機会となりました。今後も研究活動を継続することにより、生命倫理系の学術雑誌にむけた論考の執筆、さらには投稿を目指したいです。」と研究への意欲を語りました。

Hana Rinakit
早稲田大学先進理工学部生命医科学科修士1年生のHana Rinakitさんは、インドネシアご出身です。現在、所属する研究室において、腸内に存在するさまざまな微生物、いわゆる腸内細菌叢の研究に取り組んでいます。「自らが携わる生命医科学領域の研究の社会への影響についても視野を広げて考えてみたい」という思いと、幹細胞研究において最先端の研究を進めているCiRAへの興味から、三成研究室(上廣倫理研究部門)において、約2週間のインターンシップを経験することになりました。
Rinakitさんはインターンシップの期間中、ヒト由来の試料や情報を取り扱うバイオバンク※10)が担うべき社会的責任とその社会的影響について探究し、最終日には、その成果を報告しました。
発表では、個人向け遺伝子検査キット(Direct-to-Consumer Genetic Testing Kits)の販売を扱う企業と、個々人の体質や特性に応じた栄養管理・医療(とりわけ糖尿病を対象)を目的に腸内細菌叢のDNA解析を実施する企業を対象として、潜在的・顕在的な社会的課題について取り上げました。一般市民や各地の先住民族、マイノリティに対して、今後起こりうるプライバシーの侵害や搾取、差別等の懸念や危険性についても言及しました。
発表後、Rinakitさんは「今後、博士号を取得して生物学の研究者になるつもりでしたが、今回の経験は、別の選択肢もありうるのではないかといった進路を捉え直す契機になりました。」と語りました。インターンシップでの経験が、新たなキャリアの可能性を見出すきっかけになったようです。
その他のインターンシップ報告会
※1)R言語
統計やデータの解析に特化した、オープンソースのプログラミング言語。
※2)制御ネットワーク
遺伝子発現を調節する一連の因子。
※3)心筋細胞の自動能
心臓の筋肉が自ら電気信号を発生させ、拍動を繰り返す能力。
※4)HCN4
心臓のペースメーカー細胞に存在する、電流を担うチャネルタンパク質。
※5)ノックアウト
特定の遺伝子の機能を失わせて、その遺伝子の役割を研究するための遺伝子工学の技法。
※6)EVO2
2025年に米国のArc InstituteとNVIDIA Corporationが、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者とコラボレーションしてリリースしたDNA基盤モデル。
※7)シス制御エレメント
近傍に存在する遺伝子の発現を制御するDNA配列。
※8)ゼロショット性能
AIモデルにおける、未学習状態からの反応の速度や正確さを測る指標。
※9)対話型鑑賞に関する活動が掲載されている書籍
『ここからどう進む?対話型鑑賞のこれまでとこれから アート・コミュニケーションの可能性』
※10)バイオバンク
医学研究に活用する目的で、人間の体に由来する生体試料と健康や疾患に関係する情報などを収集・保管・分譲する仕組み・施設。
-
取材・執筆した人:森井 あす香
京都大学iPS細胞研究所(CiRA) 江藤研究室






















